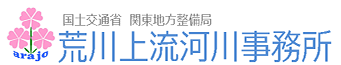-
基礎用語集【す】
|水衝部(すいしょうぶ)|
湾曲部等、洪水時に、上下流に比較して流水が堤防または河岸に強く当たる箇所を水衝部という。
|水防(すいぼう)|
洪水時に実施される河川管理施設の保護、洪水被害の防止等を目的に実施されるハード・ソフトの手法の総称。
|水防警報(すいぼうけいほう)|
河川管理者が洪水時の河川水位の状態により発表する警報のこと。
水防警報は、その区間およびその区間を代表する水防警報基準点とを定めて、その水位の程度により情報の種類を変える。水位の基準としては、指定水位、警戒水位がある。水防警報の種類は、待機、準備、出動、解除、情報、指示である。
|水防工法(すいぼうこうほう)|
洪水被害が起きる直前の対策工法、水防工法には多くの種類があるが、緊急時には各関係機関が連携して、現場の状況に適した工法を選び早急に対策を講ずる。
|水防体制(すいぼうたいせい)|
降雨の状況や出水状況により、準備、注意、警戒、緊急、非常などの体制があり、国土交通省としての業務は情報収集と連絡、水防警報、洪水予報等の発令がある。
|水防団待機水位(すいぼうだんたいきすいい)|
水防団が出動のために待機する水位。いままでの「指定水位」に対応している。
|水面勾配(すいめんこうばい)|
水面の流れの方向の沿っての勾配。
|水門(すいもん)|
河口部における高潮の影響、支川合流点における本川からの背水の影響を軽減すること等のために堤防を分断し、その部分が堤防の機能を確保できるようにゲートを設置した施設。
|水利権(すいりけん)|
河川などから水を利用する権利。
水利権には、農業用水、水道用水、工業用水などがある。また、河川法に基づき許可を得た許可水利権と永年の慣行によって成立している慣行水利権がある。
|水利使用規則(すいりしようきそく)|
許可水利権の許可書を付される書面で、その水利権の内容や条件等を記載したものをいう。
|スーパー堤防(スーパーていぼう)|
高規格堤防の別称。
堤防の敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防をいう。堤防の幅は概ね堤防の高さの30倍。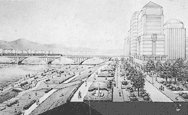
|スクリーニング(screening)|
環境アセスメントを行う事業(第一種事業)に準じる大きさの事業(第二種事業)について、環境アセスメントを行うかどうかを個別に判定する手続きのこと。
「スクリーニング」とは「ふるいにかける」という意味。
|スコーピング(scoping)|
事業者が環境アセスメントに関する予測及び評価を行う前に、環境アセスメントの項目並びに調査、予測及び評価の手法についてとりまとめた方法書を作成し、住民、地方自治体などの意見を聞く手続きのこと。
「スコーピング」とは「絞り込む」という意味。
- 国土交通省 関東地方整備局 荒川上流河川事務所
- 〒350-1124 埼玉県川越市新宿町3-12 電話:049(246)6371