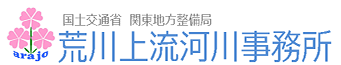-
基礎用語集【か】
|開削(かいさく)|
土留め、締切り等により地表から掘削し、構造物を施工したのち再び埋戻しを行って完成させる工法をいう。
|改修計画(かいしゅうけいかく)|
工事実施基本計画に基づいて当該河川の河川工事を行うための計画。
改修計画平面図、横断図等により河川の将来像を具体的に表現する。
|海藻と海草(かいそうとかいそう)|
陸上の植物と同様に維管束を持ち、花を咲かせて種子をつける植物のうち水中に生育する水草の中で海水中に生育するものを海草と呼ぶ。一方同じく水中に生育する維管束を持たない植物を藻類と総称し、藻類のなかで海水中に生育するものを海藻と呼ぶ。
|海中林(marine forest)(かいちゅうりん)|
藻場のうち、主として大型底生藻類(ホンダワラ類、アラメ、カジメ、ワカメ、コンブ等)が密生している場所。
|瑕疵(かし)|
管理瑕疵。主に管理の手落ちのことをいう。
何らかの「欠陥がある」という意味。法的には、法律または当事者の予想する状態の欠けている場合に広く用いられる。例えば、瑕疵ある行政行為と言えば、違法または不当な行政行為を指す。
|河床勾配(かしょうこうばい)|
河川の河床の流れに沿っての勾配。
|霞堤(かすみてい)|
急流河川に多く見られる不連続に設けられた堤防で、上流で氾濫した洪水を再度河川に導くものである。
霞堤の下流側の先端が開放されているため、洪水時は流水が堤内地に逆流するので氾濫しないよう地形に合わせて堤防を重複させる。堤防を不連続とすることにより堤内地からの河川や小水路の排水が容易となり水門、樋門等の設置を省略できる。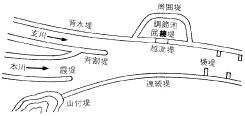
|河積(かせき)|
流水の横断面積のことで、流積ともいう。
|仮設(かせつ)|
構造物などを建設する場合、工事を行うために設け、工事が終了すると撤去する各種の設備の総称。仮設備ともいう。
|河川愛護モニター(かせんあいごモニター)|
都市河川等、ごみ等の不法投棄、流水及び河川管理施設の異常等を迅速に把握する必要がある河川に地域住民に積極的な協力を求めて、河川の清掃の保持、河川管理施設の保全等河川管理の強化を図るため設けられた制度。
|河川環境管理基本計画(かせんかんきょうかんりきほんけいかく)|
河川の水域、地先の特性等を考慮した潤いのある河川環境を創造するための基本計画。
河川空間の適正な保全と利用及び水量及び水質の総合的管理に大別される。計画策定にあたっては、河川管理者は学識経験者及び流域自治体等の意見を聴きながら総合的に実施される。
|河川環境保全モニター(かせんかんきょうほぜんモニター)|
河川環境に関する専門知識と豊かな川づくりに対する熱意を有する地域の方々の参加を得て、河川環境に関する情報の把握と河川環境の保全、創出及び秩序ある利用をきめ細かく行うため設けられた制度。
|河川管理施設 (かせんかんりしせつ)|
河川管理者が自ら管理する堤防、護岸。河川構造物。
|河川区域(かせんくいき)|
河川法が全面的に適用される河川を構成する土地をいう。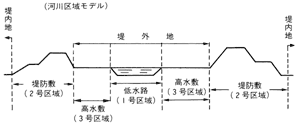
|河川現況調査(かせんげんきょうちょうさ)|
河川及び流域に関する諸元をとりまとめるための調査のこと。5年毎に実施される。
|河川構造物(かせんこうぞうぶつ)|
洪水調節、流水の正常な機能の維持等の治水効果の増進と適正な河川管理のために必要な諸施設の総称。
|河川敷 (かせんしき)|
堤防と流水が常に存する土地との間にある土地の事をいう。高水敷ともいう。
→本ページ「河川区域」参照
|河川整備基本方針(かせんせいびきほんほうしん)|
河川法第16条に基づいて策定される長期的な河川工事及び河川の維持(整備)についての基本となるべき方針(基本計画)。
平成9年に河川法が改正され、それまでの治水、利水を主な目的とした工事実施基本計画(略称:工実)に代わるもので、策定及び変更の際には河川審議会の意見を聞かなければならない。
|河川整備計画(かせんせいびけいかく)|
河川法第16条の2に基づいて策定される計画で、長期的な方針(基本計画)である河川整備基本方針に沿って段階的な目標を定め、計画的に河川整備を実施するための計画。
河川整備計画は案を策定する段階で学識経験者の意見を聞くことと流域住民の意見を聞くための措置(公聴会の開催等)を講じることとなっていて、河川の具体的な整備に流域住民等の意見反映することが平成9年の河川法改正時に追加され義務づけられた。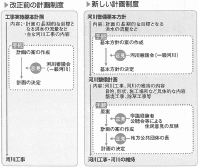
|河川台帳(かせんだいちょう)|
河川現況台帳と水利台帳の二つに分かれる。河川、河川保全区域、河川管理施設、河川使用の許可等を一定の様式によりとりまとめられた台帳のこと。
|河川法(かせんほう)|
河川について洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保存と開発に寄与し、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的としている。(法第1条)
|河川防災ステーション(かせんぼうさいステーション)|
河川沿いに人口、資産の集積している地域や閉鎖型氾濫地域において、破堤などの被害を防止し被害を最小限にくいとめるために適切な水防活動及び迅速な緊急復旧活動を実施する拠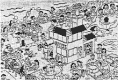 平常時
平常時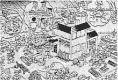 洪水時
洪水時|川保全区域 (かせんほぜんくいき)|
河岸または河川管理施設を保全するため必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域に隣接する一定の区域をいう。
河川保全区域の指定は、河岸または河川管理施設を保全するため必要最小限度の区域に限ってするものとし、地形、地質等の状況によりやむを得ないと認められる場合を除き、河川区域の境界から50mを超えてしてはならない。
|河川水辺の国勢調査(かせんみずべのこくせいちょうさ)|
河川事業、河川総合開発事業、河川管理、ダム管理を適切に推進するための基礎情報として、河川を環境という観点からとらえた定期的、継続的、統一的な河川に関する調査をいう。
河川水辺の国勢調査
├ 河川調査
├ 魚介類調査
├ 底生動物調査
├ 動・植物プランクトン調査(ダム湖のみ)
├ 植物調査
├ 鳥類調査
├ 両生類・爬虫類・ほ乳類調査
├ 陸上昆虫類等調査
└ 河川空間利用実態調査・ダム湖利用実態調査
|河川立体区域(かせんりったいくいき)|
河川管理施設等に係る河川区域を地下又は空間について一定の範囲を定めた(指定した)立体的な区域。
|カルバート(culvert)|
道路、水路などの空間をうるために、盛土あるいは地盤内に設けられる構造物。
力学的特性から剛性カルバートとたわみ性カルバートがあり、剛性カルバートにはボッックスカルバート、門形カルバート、パイプカルバートなど、たわみ性カルバートにはコルゲートメタルカルバートがある。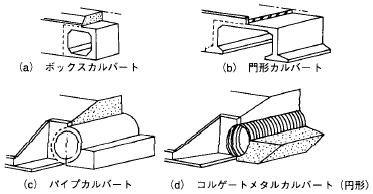 カルバート(culvert)図解
カルバート(culvert)図解|環境アセスメント (environmental impact assessment)(かんきょうアセスメント)|
正式には環境影響評価。
土地の形状の変更、工作物の建設等の事業の実施が環境に及ぼす影響について、あらかじめ事業者自ら適正に調査、予測及び評価を行うとともに環境の保全にための措置を検討し、総合的に評価することで、事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保するもので、そのための住民等の外部手続きを含む。
|環境基準 (environmental quality standards)(かんきょうきじゅん)|
「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」(環境基本法第16条)のこと。大気、騒音、水質、土壌の4種類について定められている。
環境基準は、維持されるべき環境の状態の政策的な目標であり、公害の発生源を直接規制するための基準(規制基準)とは異なる。
(「98%値、2%除外値」参照)|環境基本計画 (かんきょうきほんけいかく)平成12年12月22日閣議決定|
環境基本法第15条に基づき、環境に保全に関する施策の総合的かつ計画的推進を図るための定められた計画で21世紀初頭における環境政策の展開の方向を明らかにしている。
この計画では、長期的目標として、「循環」「共生」「参加」及び「国際的取組」の4つを掲げている。
|環境ホルモン (environmental endocrine disruptors)(かんきょうホルモン)|
「動物の生体内に取り込まれた場合に、本来、その生体内で営まれている正常ホルモンの作用に影響を与える外因性の物質(H10.5“環境ホルモン戦略計画 SPEED’98”環境庁)のこと。
環境省をはじめ国内では一般的に、“外因性内分泌攪乱化学物質”といい、動物や人間の体の中で、何らかの形でホルモンの働きに作用し(体内のホルモンバランスを崩す)、精子の減少、子宮内膜症、ガンなどを引き起こす科学物質を指している。環境省において、疑われる化学物質として当初67物質を定め(H10.5 SPEED’98)、その他2物質削除され65物質(H12.10 内分泌攪乱化学物質問題検討会)とされている。
(「ダイオキシン類」参照)|関東広域情報ネット構想 (かんとうこういきじょうほうネットこうそう)|
関東地方整備局で整備している河川や道路管理用の光ファイバー網を活用し、防災情報等を、自治体・防災関係機関と共有したり、メディアを通じて市民へ提供を行う。平成12年11月に策定された。
|関東地方整備局防災業務計画書 (かんとうちほうせいびきょくぼうさいぎょうむけいかくしょ)|
関東大地震や阪神・淡路大震災と同程度、東海地震、南関東直下型地震等の地震発生を想定して局及び事務所レベルの対策書。事前準備、発災後等の動員計画、通信連絡体制等について記述されている。
|感潮河川 (かんちょうかせん)|
河口部の潮の干満の影響を受ける河川または区域。
- 国土交通省 関東地方整備局 荒川上流河川事務所
- 〒350-1124 埼玉県川越市新宿町3-12 電話:049(246)6371