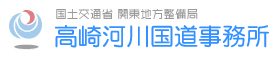かわづくり
-
河川からのお知らせ
体験体感 「烏川・神流川・鏑川・碓氷川」 -水辺や流域の魅力を大発見!-
歴史建造物を訪ねる旅
歴史建築ファンにもたまらないのが上州の旅。高崎のシンボルとなった大観音から、隠れた名建築、パワースポットとして知られる神社仏閣など、見どころは数えきれない。
高崎白衣大観音

優しいまなざしで平和を見守る高崎のシンボル
観音山の頂上に立つ白衣観音像で、関東八十八ヵ所霊場第一番札所として多くの参拝客を集めている。1936(昭和11)年、高崎市の実業家・井上保三郎氏が社会平安などを祈願して建立したもので、今では市のシンボルとなっている。像の高さは41.8mで、白衣の名の通り真っ白なお姿で青空神流川頭首工 をバックにたたずむ様子は圧巻だ。国の登録有形文化財。旧下田邸書院

風格と優美さを兼ね備えた書院
箕輪城主長野氏の重臣・下田大膳正勝の子孫が代官として居を構えた屋敷跡。江戸時代の書院が残り、庭園とともに貴重な近世の様式を今に伝えている。金鑚神社 多宝塔
 金鑚神社
金鑚神社 金鑚神社 多宝塔
金鑚神社 多宝塔厳かな空気に包まれた古社
金鑽神社は日本武尊が東征の際に創建したと伝えられる由緒ある神社。境内にある多宝塔は国指定重要文化財。塔の高さ約13.8m、屋根は二重の「こけら葺き」。武蔵七党の豪族・安保氏が子孫の繁栄を祈って建立したものと言われている。少林山達磨寺

縁起だるま発祥の地
観音山丘陵の端に位置する少林山達磨寺は、黄檗宗の寺院。有名な縁起だるまは天明の飢饉の後、九代目東嶽和尚が苦しい農民の副業にと、達磨の張り子づくりを伝授したのが始まりと伝えられる。玉村八幡宮と昇龍の松・勝運の松
 玉村八幡宮
玉村八幡宮 昇龍の松・勝運の松
昇龍の松・勝運の松朱塗りの本殿は国指定重要文化財
鎮守の森に囲まれた玉村八幡宮。源頼朝が鶴岡八幡宮を勧請して角渕に創設したのが始まりで、江戸初期に今の地に遷座したと伝えられる。敷地内の昇龍の松・勝運の松は必勝祈願のパワースポットとしても人気急上昇中だ。暮らしを支える治水・利水施設
豊かな河川の水とともに産業と生活の基盤を築いてきた群馬県だが、一方では治水や利水の整備に向けた治水事業の歴史も脈々と生き続けています。治水・利水施設に目を向けることで、地域の歴史も見えてくる。
神流川頭首工


自然と調和した美しい農業用水施設
頭首工とは、河川の流水を用水路に引き入れる施設。かつて神流川流域では農業用水をめぐる「水争い」が絶えなかったが、これを解消するため、埼玉県営用水改良事業により6ヵ所あった堰を統合、現在の神流川頭首工を完成させた。平成16年に国営かんがい排水事業で改修された建物は切妻屋根・高窓などの養蚕にまつわる建築様式を採用。また周辺の自然とも調和した頭首工となっている。
長野堰(長野堰用水円筒分水)


高度な技術で1000年前に開削された用水路
長野堰用水は、古くは室町時代から農業や市民生活に利用され、高崎市の発展を支えた施設だ。地形が台地上で河川の水を流入させることが困難だったこの地域で長野堰の開削が始まったのは約1100年前。当時の高い土木技術も注目されている。現在では烏川から最大5.8トン/秒を取水し、幹線水路は15ヵ所の水門で分水しながら、円筒分水堰(写真左)でさらに4支線に分岐する。八ッ場ダム

68年の時をかけて完成した絶景のダム
2020(令和2)年、利根川支流の吾妻川中流域に完成した八ッ場ダムは、洪水調節や流水の正常な機能の維持、水道および工業用水の新たな確保、発電などを担う多目的ダムだ。堤高116mの堤体上を散策できる他、展望デッキも整備され、さまざまな角度からダムを堪能できる。またダム周辺にも水上アクティビティやキャンプ・バーベキュー施設、湖畔公園などがあり、観光人気も高まっている。なるほど!やんば資料館

ダム本体工事と関係地域の情報を発信する拠点として、「地域の成り立ち」、「事業経緯や目的」、「八ッ場ダム周辺の立体模型」、「本体工事の動画」などを展示している。ダム見学と併せて見ておきたい。
下久保ダム

自然と調和する人工美は見もの
藤岡市(群馬県)と神川町(埼玉県)にまたがる神流川に建設された多目的ダム。完成は昭和43年。同時に生まれたダム湖は神流湖と命名された。堤体の長さはコンクリートでできたダムの中では日本最長。また、主ダムと副ダムがほぼ直角になっている構造も珍しい。自然豊かな地域にあって調和のとれた人工美を造り出しており、周辺は四季折々の自然を楽しめるハイキングコースになっている。神流川と三波石峡の資料館

下久保ダム管理所1階に併設されている資料館。下久保ダムやダム周辺の川についての資料が展示されている。入場は無料。