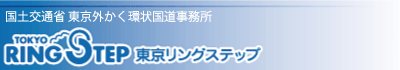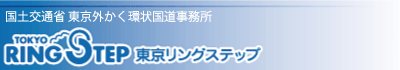東京外かく環状道路(関越道〜東名高速)(以下「外環」という)計画に関する話し合いの場としてPI外環協議会(仮称)(以下「協議会」という)設立に向けて、これまで準備会では9回の会合を重ね検討してきた結果、以下の様に議論のとりまとめを行い協議会の運営に生かしていくものとする。
|
1.基本認識
|
| (1)原点について |
| ・ |
外環の計画については、これまでの経緯を十分に踏まえて、実質的には、現在の都市計画を棚上げにし昭和41年都市計画決定以前の原点に立ち戻って、計画の必要性から議論をする。
|
| (2)必要性の有無(効果と影響)について |
| ・ |
必要性の議論については、計画ありきではなくて、もう一度原点に立ち戻って、計画の必要性から検討する。
|
| ・ |
協議会は結論を出す場ではないが、公開して進めるので、より多くの人にその議論の内容を知ってもらうことに意義がある。
|
| ・ |
このため、協議会での必要性の議論は、その後の計画の検討をどのようにしていくかということに重大な影響を与えるものと考えられ、社会的にそれを無視することは難しいと考える。
|
| ・ |
協議会での議論やその他の幅広い意見を踏まえ、様々なプロセスの中で外環計画の意義について、社会全体で検討するものと考える。
|
| ・ |
その中には、上位計画における議論も含んでおり、そのプロセスを経た結果、社会全体として外環計画の意義がないとの社会的判断がされれば、事実上計画を休止することもあり得る。
|
2.協議会の基本的な考え方
|
| (1)目的 |
| ・ |
協議会は、外環について、原点に立ち戻り計画の構想段階から幅広く意見を聞き計画づくりに反映するため、パブリック・インボルブメント(PI)方式で話し合うことを目的とする。
|
| (2)位置づけ |
| ・ |
協議会は、沿線7区市の関係者代表と国・都の話し合いの場とする。また、この協議会の他、沿線7区市の各地域における個別説明会やオープンハウスなどで幅広い意見を十分に把握する。さらに、東京圏の関係者に、ヒアリングをするなど、広域の意見の把握に努める。これらの把握した意見については、相互に共有し尊重するように努める。 |
| ・ |
外環についてPI方式で話し合いを進めていくにあたっては、将来のルール化にも生かせるPIの模範となるよう努める。 |
| ・ |
協議会は適切な頻度で開催するものとし必要な限り話し合い民主的に運営する |
| ・ |
協議会においては、構成員が対等の立場で話し合いができるよう、国及び都は就任依頼の方策について検討する。
|
| (3)話し合い内容 |
| ・ |
まず、必要性の有無(効果と影響)について議論する。 |
| ・ |
必要なデータ・資料等は、提示することとし、もし提示できない場合は、その理由を明確にする。
|
| <効果と影響> |
| ○首都圏における自動車交通について |
| ○外環を整備する場合の効果 |
| ・ |
環境面での効果、地域交通への効果、渋滞の緩和、広域交通の利便性の向上 |
| ○費用対効果 |
| ○環境に与える影響 |
| ・ |
大気への影響(換気塔周辺、JCTやIC周辺、騒音、振動の影響(JCTや)IC周辺、地下水に与える影響) |
| ○生活に与える影響 |
| ・ |
地域分断、移転の影響、JCTやIC周辺の交通集中
|
| (4)構成 |
| 構成は以下の通りとする。 |
○関係者代表
|
| ・ |
外環沿線の7区市(練馬区、杉並区、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、世田谷区)で、外環計画に関する活動をしている方(賛成、反対は問わない) |
| ○人数 |
| ・関係者代表 |
| 7区市の推薦 |
14名程度 |
| 国、都の推薦 |
若干名 |
| ・7区市の担当者 |
7名 |
| ・国、都の担当者 |
4名 |
| 計 |
25〜30名程度 |
|