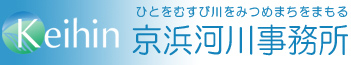| 縄文時代(B.C.10000~B.C.300年頃) |
| 中期末 |
中流から上流にかけて平坦な洪積丘陵上に湧泉周囲集落ができる |
| 敷石住居も作られる(八王子市船田遺跡・秋川市羽ヶ田遺跡・多摩ニュータウン遺跡) |
| 後期 |
下流域に集落ができる |
| 弥生時代(B.C.300~A.D.300年頃) |
| 後期 |
村が各所にできる |
| 方形周溝墓 が伝わる |
| 古墳時代(300~592年頃) |
| 前期 |
大きな 前方後円墳が築造される |
| 狛江の亀塚(帆立貝型古墳)は多摩川流域ではじめて本格的な濠(お堀)をめぐらした古墳 |
| 中期 |
川崎市域の古墳に埴輪の樹立が盛ん |
| 後期 |
人口急増と稲作・畑作の躍進期 |
| 多摩川流域に横穴式石室・横穴墓が現れる |
| 飛鳥時代(592~710年) |
| 646 |
大化2 |
「武蔵国」成立(19郡)、大和朝廷の下に入る |
| 686 |
朱鳥1 |
「武蔵国」の名がつき、21郡を含める。府中市大国魂神社近くに国庁が設置される |
| 687 |
持統1 |
百済人、武蔵に入植 |
| 奈良時代(710~794年) |
| 772 |
宝亀3 |
川崎市で火葬が行われ始める |
| 平安時代(794~1192年) |
| 818 |
弘仁9 |
7.- 相模・武蔵・下総など関東諸国に地震あり、被害甚大 |
| 843 |
承和10 |
6.25 武蔵国など18か国が飢饉 |
| 858 |
天安2 |
武蔵国水害 |
| 878 |
元慶2 |
9.29 関東に大地震あり、相模・武蔵の被害が特に甚しい |
| 鎌倉時代(1192~1333年) |
| 1241 |
仁治2 |
10.22 幕府、武蔵野に多摩川から水を引き、水田をひらくことを議定 |
| 12.- 多摩川に堰堤を築く |
| 1333 |
正慶2
元弘3(北朝) (南朝)
|
5.- 武蔵国分寺焼失 |
| 室町時代(1333~1573年) |
| 1489 |
延徳1 |
府中馬市の盛況 |
| 1555 |
弘治1 |
北条氏康が武蔵国を集中的に検地する |
| 安土・桃山時代(1573~1603年) |
| 1585 |
天正13 |
8.28 武蔵国大風洪水 |
| 1590 |
天正18 |
多摩川大洪水。現川崎市多摩区内の流路が北遷し、ほぼ現在の位置となる |
| 1597 |
慶長2 |
2.1 小泉次太夫、六郷用水及び二ケ領用水の開削に着手 |
| 1600 |
慶長5 |
7.- 六郷橋(長さ120間)完成 |