|
|
 |
人馬の「継ぎ送り」とはどういうことですか? |
 |
「継ぎ送り」とは、江戸幕府の公用で旅をする人たちのために、その人たちの荷物を宿場から宿場へと、次から次へリレー方式で受け継いで送ることをいいます。
このため各宿では、荷物を運ぶための人足と馬を常備することが義務づけられていました。はじめ東海道の各宿には36疋の馬を備えさせましたが、寛永15年(1638)以降、100疋の伝馬と100人の伝馬人足の設置および継立が義務づけられました。
このとき、伝馬朱印状を持つ者には伝馬を無料で提供しなければならず、その代わり、宿場は土地の税金が免除されるなどの特典や、公用の荷物以外は有料とし、その際の駄賃稼ぎが宿場の特権として認められていました。
初代広重が描いた浮世絵には継ぎ送りの光景がよく描かれています。題名も「人馬宿継之図」というもので、問屋場の前で馬から降ろし、新しい馬に積み替えています。
問屋場では武士の供が宿役人に書類を提出したのを、宿役人が証文と思われる文書を確認している様子です。
|
図版:東海道五拾三次之内 庄野「人馬宿継之図」
初代広重 行書版 神奈川県立歴史博物館蔵 |
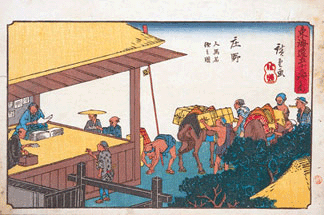 |
|
 へ戻る へ戻る

 へ進む へ進む
|
|