|
|
 |
「旅籠屋」(はたごや)と「木賃宿」(きちんやど)はどう違うのでしょうか? |
 |
一般の旅行者が宿泊するところには旅籠屋と木賃宿がありました。
旅籠屋と木賃宿との違いは、食事が付いているか付いていないかの違いです。
旅籠屋では夕食と朝食を出し、店によっては昼食の弁当を出すところもありました。
一方、木賃宿は、旅人が米を持参し、薪代を払って自分で米を炊くかまたは炊いてもらいます。「木賃」とはこのときの薪の代金、つまり木銭(きせん)を意味しています。
江戸時代以前には木賃宿が宿泊の本来の姿でしたが、庶民の旅が盛んになるにしたがい、次第に旅籠屋が増え、宿代も天保年間(1830〜1844年)には旅籠屋は木賃宿の5倍以上もするということで、木賃宿は安宿の代名詞となってしまいました。場所も宿場のはずれなどにありました。
|
図版:東海道五拾三次之内 赤坂 「旅舎招婦ノ図」 初代広重 |
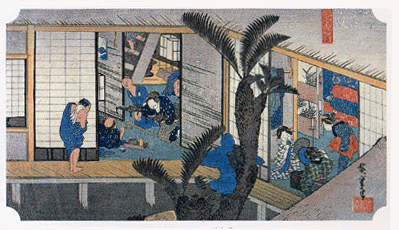 |
|
 へ戻る へ戻る

 へ進む へ進む
|
|