|
|
 |
古代の東海道と江戸時代の東海道ルートはどう違うのですか? |
 |
古代には、東海道という名前に行政区画という意味があったことは「Q1 東海道って、なぜ「海道」と書くのですか?」で説明しましたが、10世紀初めに編纂された『延喜式』に、東海道に含まれる国々の名が書かれています。都から、伊賀、伊勢、志摩、尾張、参河(みかわ)、遠江、駿河、伊豆、甲斐、相模、上総、下総、安房、常陸の14カ国がそれにあたります。
ですから、これらの国々の国府(国司が政務をとった役所)を通って平安京(京都)にいたる道が、街道としての東海道ということになります。古代には、この国府と国府を結ぶ道を駅路といい、駅路には30里(16km)ごとに駅家(うまや)が設けられ、東海道には、それぞれ駅馬10疋がおかれていました。
そこで、古代の東海道のルートを調べる場合、これらの国府や駅家がどこにあったかがポイントになります。相模国の国府の所在地についてもいくつかの説があり、確定されていませんが、現在のところ、図のようなルートが想定されています。
|
図版:相模国の駅路 |
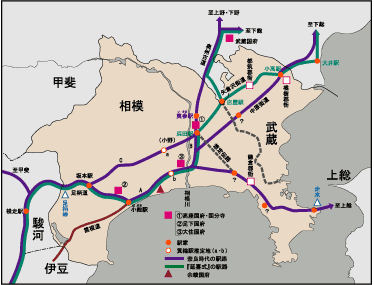
図をクリックしてください。詳細があります。 |
|
 へ戻る へ戻る

 へ進む へ進む
|
|