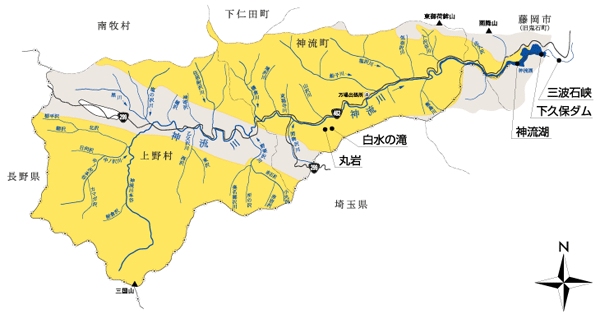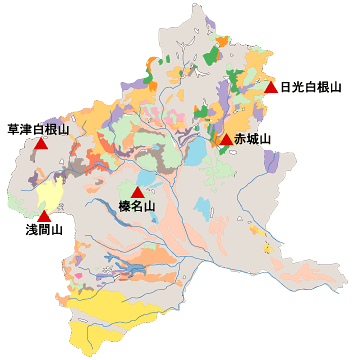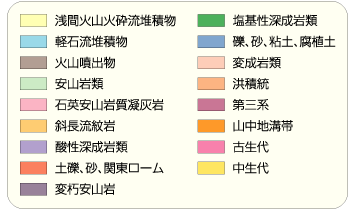流域情報
-
神流川流域
神流川流域の地質
群馬県の地質
利根川流域のなかでも群馬県の地質構造は複雑で、三波川結晶片岩や山中地溝帯など、日本列島の地質構造を代表する岩石や地質構造が分布しています。
南北に走る構造帯は東から足尾帯、片品構造帯、上越変成帯があり、これらを東西に切るように走るのが三波川帯、秩父帯です。群馬県では、これら古生層以降の地質が最も古く、群馬県の背骨を形成しています。こうした背骨の地質は、本州地向斜とその後の本州造山運動の過程で形成されました。
赤城、榛名、子持、小野子や、浅間、草津白根、武尊などの諸火山は、いずれも第四紀に入ってから陸上で噴火を始め、洪積世の末頃にはほとんど完成していたとみられています。各火山の噴出物はそれ以前の地層・岩石を広く覆って、それぞれの火山層を形成しました。神流川流域の地質
神流川流域の地質は西南西~東南東の走向を示し、複雑に褶曲した秩父古生層、中生層ならびに長瀞系の結晶片岩等からなっています。中生層と秩父古生層との間は多く断層をなしており、この地域では地層は破砕されて、いわゆる破砕型の地すべり地帯が多くなっています。
(出典:群馬の砂防)