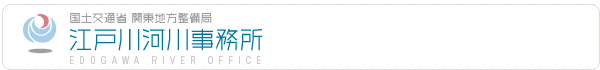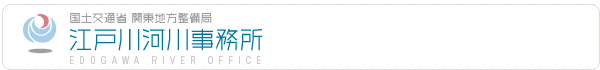|
|
| 「あ」 |
|
|
|
石だし(いしだし)
石だしとは、伝統的河川工法の一つであり、石造りの水制の出しのことです。古来、砂利河川あるいは急流河川に施工された水制で、全部割石をもって築き立てるか、あるいは盛土の表面に空積み、練積みの割石張り、または玉石張りを行うものがあります。 |
|
|
|
石張り(いしばり)
石張りとは、のり面保護の目的として用いられる河川護岸工の一種です。通常のり勾配が1対1より緩い勾配ののり面を保護するために用いられます。材料としては、玉石、割石、雑石が使われ、張り方には空石張りと練石張りがあります。 |
|
|
|
維持流量(いじりゅうりょう)
舟運、漁業、景観、塩害の防止、河口閉塵、地下水の維持、動植物の保存、流水の清潔の保持及び河川管理施設の保護などを総合的に考慮し、渇水時において維持すべきであると定められた流量。河川において、流水の正常な機能を維持するために必要な流量で、維持用水ともいう。現在では洪水防御の場合と同様に、渇水流量の極値分布より統計論を適用して維持流量を合理的に決定する方法が検討されている。 |
|
|
|
一枚のり(いちまいのり)
これまでの堤防は、のり面の途中に平場を設けていました。これを小段と呼びます。一枚のりはこの小段がないものです。 |
|
|
|
一級河川(いっきゅうかせん)
一級河川とは、「国土保全上又は国民経済上、特に重要な水系で制令で指定したもの(いわゆる一級水系)に係る河川で、国土交通大臣が指定したもの」をいいます(河川法第四条第一項)。 |
|
|
|
右岸・左岸(うがん・さがん)
河川の両岸について、上流から下流に向かって右側の河岸を右岸、左側の河岸を左岸という。 |
|
|
|
牛枠(うしわく)
牛及び枠類とは、伝統的河川工法の一つであり、水制に多く使用されています。1本の合掌木にむね木を斜めに載せ、合掌木の脚をはり木で連結して四面体の枠をくつったもので、重りの蛇籠を載せて沈めます。その形が牛に似ており、杭打ちのできない玉石や砂利の河川で水制や根固めに適した工法です。 |
|
|
|
越水(えっすい)
越水とは、増水した河川の水が、堤防の高さを超えてあふれ出す状態のことを言います。あふれた水が堤防の裏のりを削り、破堤を引き起こすことがあります。 |
|
|
|
表のり裏のり(おもてのりうらのり)
「のり」とは堤防の法面の略で、堤防の上から見て川側ののり面を表のり、市街地側ののり面を裏のりと言います。 |
|
|