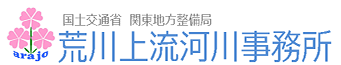荒川を知ろう
-
荒川の自然
生き物図鑑
昆虫(1/2)
幼虫をヤゴとして水の中で暮らすトンボ類、葉を食べて成長する蝶類、樹液に集まるクワガタやカブトムシなど、草地を好むバッタ、スズムシ、マツムシなど。水と草と花と木の自然が残る荒川には、たくさんの虫たちがそれぞれの好みにあった場所で暮らしています。中流域の砂れき地などにすむカワラバッタ。ハンノキ林に生活する埼玉県の蝶・ミドリシジミ。いずれも荒川の自然を構成する特徴的な生き物ですが、今では「貴重種」になっています。
カワラバッタ

植生のほとんどない砂礫河原に生息するバッタです。体は砂の色とそっくりですが、飛ぶと後翅の青色が鮮やかでよく目立ちます。
クツワムシ

大型のキリギリスです。つる植物が生い茂った藪や草深い草原にすみ、8~9月頃はガシャガシャガシャとやかましく鳴きます。
クルマバッタ

明るい疎らな草原にすむ大型のバッタです。トノサマバッタに似ていますが、飛ぶと後ろ翅の黒い帯がはっきり見えるのが特徴です。
スズムシ

河川敷の草深い藪やススキ原などに生息し、リーンリーンと鳴く声が古くから親しまれています。
ノコギリクワガタ

雑木林やヤナギ林の樹液に集まる大型の甲虫です。幼虫は朽ち木を食べ、大型のオスでは湾曲した大きな大アゴを持ちます。
オナガササキリ

ススキやオギなどの高茎草原に生息する小型のキリギリスです。メスの産卵管が長大なためオナガの名がつきました。
ヤマトシリアゲ

草原や林縁で見られる肉食性の昆虫です。オスの腹端が上方に巻き上がっていることからシリアゲムシという名がつきました。
ヘイケボタル

6月下旬から8月にかけて水田や低湿地で発生するホタルは、発光することでオスメス間のコミュニケーションをとっています。
コガネグモ

初夏のころ農耕地周辺や草原で見られる大型で造網性のクモです。近縁のナガコガネグモよりも早い時期に見られます。
オオムラサキ

エノキを食樹として年に1回初夏に発生する日本最大のタテハチョウです。オスの翅表は青紫に輝きます。日本の国蝶。
ギンイチモンジセセリ

オギなどの草原に生息する小型のチョウです。春から秋まで3回ほど繁殖しますが、春に出現する個体には裏翅に鮮やかな銀白色の一文字模様があります。
ゴマダラチョウ

エノキを食樹として年に2回発生する大型のタテハチョウです。幼虫で越冬し、成虫はよく樹液を訪れます。
コムラサキ

ヤナギ類各種を食樹として通常年に2回発生するタテハチョウです。オスの翅表は光線の具合によって紫色に輝きます。
ミドリシジミ

湿地に見られるハンノキを食樹とする小型のチョウです。初夏の頃に出現し、夕暮れ時になるとハンノキ林の樹冠部を素早く飛び回ります。
ミヤマシジミ

砂礫河原に生えるコマツナギを食草にしている小型のチョウです。砂礫河原本来の環境が年々失われ、全国的にも減少が著しいチョウのひとつです。
アジアイトトンボ

湿地、池沼など水辺で最も普通に見られるイトトンボです。メスの若い個体はオレンジ色ですが、成熟とともに暗緑色に変化します。