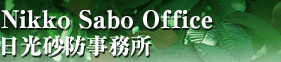|
砂防堰堤のなかま、石造品の世界
日光彫や日光杉に代表される日光の「木の文化」。一方で、男体山などの山々や大谷川を母体として地域に息づく「石の文化」を忘れていませんか? 東照宮造営に際しては、全国から大工と同じくらい多くの石工が日光に集まり、石の土台を築き、数々の石造品を彫り上げていきました。日光街道のにぎわいを背景に、今市市の石仏や、日光型と呼ばれる日光市の庚申塔や燈籠など、地域特有の形態を持った、実に多くの隠れた文化財が今に伝えられています。日光砂防事務所では、砂防堰堤の国登録有形文化財への登録とともに、そうした隠れた観光資源に着目し、日光郷土センターなどを中心に、日光市と共同で砂防堰堤をはじめとする文化財の紹介につとめています。

| 十王とは、大王と呼ばれる閻魔王と、地獄で死者の生前中の功罪をさばく九王の総称です。この十王像は、十王堂のご本尊としてお堂に祀られていましたが、昭和30年9月の大暴風雨で大破し、その後、大修繕の際に現在地に移りました。
|

|

|
|


寛文2年(1662年)旧暦6月に、当時日光山内東側にあった稲荷町が大洪水にのみ込まれました。そのときの死者140名の供養のために、翌年の寛文3年(1663年)に2基の笠塔婆が建立されました。
|
|

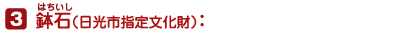
鉢石のある上鉢石町付近は、中世紀までは坂本と呼ばれていましたが、元和から寛永にかけての東照宮造営を契機に、「鉢石宿」と呼ばれるようになりました。勝道上人ゆかりの名石として、「鉢を伏せたような形」がその名の起こりで、昔から石の周囲には柵を設け、しめ縄を張って神聖視されてきました。
|
|


護摩壇とは密教に基づいて祈祷を行う時に使うもので、中央の爐に火をともして供物を献じ、いろいろな祈願をします。日光地方は、山岳修験の影響もあり、野外で護摩壇が使用されるため、常設でしかも石造が多いのが特徴です。
|
|


60日に一度訪れる干支の庚申の夜、人が眠ると体内にすむ虫・三尸が天帝に日頃の行いを告げるという中国の道教を起源に、その日は庚申の札を貼り、夜を徹して集う貴族の
慣習、庶民の民間信仰になりました。駒形で、日と月を表す円の下に合掌して向かい合うサル、さらには塔の下部に睡蓮が配置される形態が、「日光型」庚申塔の特徴です。
|
|


明治35年9月の大谷川の洪水で憾満ヶ淵にある「並び地蔵(化け地蔵)」も相当数が流失しました。頭部だけの地蔵菩薩は、この並び地蔵のうち2体あった「親地蔵」のひとつです。
|
|


三体並んだ石仏、通称「導地蔵」の中央の地蔵尊は、天文19年(1550年)で、日光で最古の年記銘があります。右は寛永13年(1636年)の地蔵尊。左の文禄5年(1596年)の阿弥陀如来は、日光では最古の年記銘です。全体に簡素で、日光土着の石工の手による素朴な味わいを持っています。
|
|


山内北野神社の石造品群は、菅原道真公を祀った天神塔と石祠(石のほこら)を中心に構成されています。中央に祀られている天神塔は、自然石に梅鉢紋が彫られているのが特徴です。石祠は元文5年(1740年)のもので、天神塔と一緒なのは、日光ではここだけです。
|
|


日光の燈籠には、方形で中台を持たず、火袋と竿の部分を一石一体にした大型のものがあります。これを「日光常夜燈石燈籠」と呼ぶ方もいます。
|
|


日光では浄光寺墓地にある座禅院権別当墓(日光市指定文化財)が有名ですが、清滝寺の歴代住職が眠る歴代墓地でも、平成4年からの日光市文化財保護審議会の調査で新たに11基の中世期の五輪塔が確認されました。
|
|


宝篋印塔は、「宝篋印陀羅尼経」を納めた塔のことです。日光では中禅寺湖上野島と滝ヶ原の2基が知られていましたが、清滝寺歴代墓地で新たに3基が発見されました。
|
|


日光の僧侶像はいずれも日光山に関係する僧と考えられます。清滝寺歴代墓地の僧形像は、天台宗での最高位の僧の装束を身にまとっており、慈眼大師天海などの相当に高名な僧侶ではないかと思われます。
|
|
 |
|