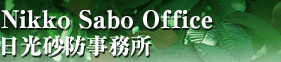|
斜面の山肌が露出している崩壊地は、放置したままでおくと、山の崩壊が拡大して、下流へ土砂が流出してしまいます。
また、崩壊場所では、山の表面の土が移動しやすく、植物の生育が困難で、ますます崩壊が拡大するという悪循環になってしまいます。
山腹工とは、こういった山の崩壊地に、斜面の土砂崩れを防ぐ柵や壁を設置したり、植物がよりよく生育できるように、斜面を固定する基礎工事を施し、草木を植栽することによって緑化を進め、土砂が流出しない安定した地盤づくりをする工事のことです。 |
 |

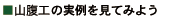
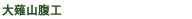
大薙は男体山の東南の斜面にあたり、薙の中では最も大きく、崩壊斜面は尾根まで達しています。
この崩壊地は、約300年前の天和3年(1683年)の大雨を伴った大地震によって発生したとされています。標高1075メートルより山頂に至る山腹をつらぬき、平均勾配28度、薙巾300メートル〜400メートル、浸食深70メートル〜100メートル、現在もなお崩壊を続け、自然復旧の見込みは殆どありません。
大薙山腹工は、崩壊地からの土石流が日光市街に大きな被害をもたらすのを防止するため、日光を代表する男体山の風景美を維持しながら、崩壊地を緑豊かな自然に復元します。
工事は、昭和25年(1950年)から着手し、方等上流砂防堰堤を含め、堰堤工、谷止工50基計画に対し既設43基、緑化工15ヘクタール計画に対し3.8ヘクタール施工してきました
|
|
|
|