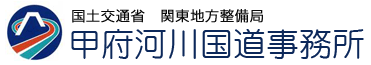かわづくり
-
伝統的治水施設の保全と整備
甲州舟運
富士川舟運の終焉(しゅうえん)
高瀬船から鉄道へ
 鰍沢町(現・富士川町)が再現した高瀬舟
鰍沢町(現・富士川町)が再現した高瀬舟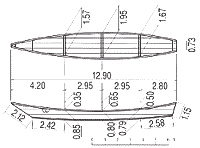 高瀬舟の基準図(明治18年までの標準型)
高瀬舟の基準図(明治18年までの標準型)慶長12年(1607)、角倉了以の手による航路開削工事に始まり、5年間の歳月を経て「高瀬船」による富士川の舟運は開始された。年貢米や塩を中心とする物資の輸送から人々の足として欠かせないものとなっていくが、明治時代になると、社会情勢が大きく変化する中で、取り扱う物資も多様化すると共に増大し、また、利用する人々も増加したことから航路の改修はさらに進み、航行する舟も大型化されたり、帆舟やプロペラ舟も登場するようになり、中頃には最盛期を迎える。
しかし、世界に門戸が開かれ海外から様々な高い技術が導入される中で、明治22年に東海道線が開通し、同36年には中央線が開通したことにより舟運は衰退を余儀なくされ、昭和3年の身延線の開通に伴い、喜びと苦しみ、そして幾多の犠牲者と共に歩んだ316年間にわたる使命に終わりを告げたのである。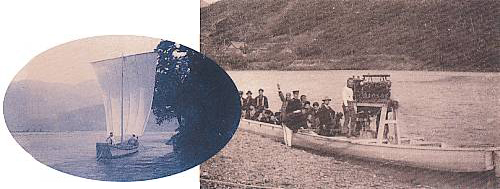 帆舟の航行・飛行艇(プロペラ舟)
帆舟の航行・飛行艇(プロペラ舟)