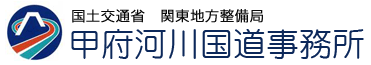かわづくり
-
伝統的治水施設の保全と整備
甲州舟運
舟運発達の背景
何故!急流富士川に
 角倉了以の角倉了以顕彰碑(鰍沢河岸跡地)
角倉了以の角倉了以顕彰碑(鰍沢河岸跡地)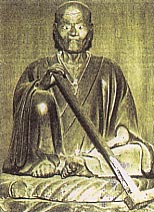 角倉了以木像(京都大悲閣蔵)
角倉了以木像(京都大悲閣蔵)我が国においてはかなり古い時代から、既に河川における舟運が行われていた。このことは「延喜式」(律令の施行細則905~927)の中で「水駅の制」が示されていることからも頷ける。当時の首都圏である畿内(きない:現在の近畿地方)の大和川、淀川は地方の国から奈良や飛鳥、京都などの都に貢ぎ物を運ぶ舟で賜わっていた。しかし、地方の川において舟運が開かれるのは江戸時代になってからのことで、理由はいくつか考えられる。一つは、地域とか川全体を統治する政治機構が確立できなかったこと、一つは、当時の造船技術とか操船技術は秘伝とされ、地方への伝わりが遅れたこと等であろう。
富士川に舟運が開かれたのは、江戸時代の始めである。実際に航行が開始された年は定かではないが、山梨県市川三郷町の円立寺にある「天神画像」に書かれた日付から、慶長17年(1612)頃と推定される。その前の慶長12年(1607)徳川家康の命により「角倉了以」(*)が航路の改修にのり出し、5年間の歳月を要して完成させたものであるが、土木技術が十分でなかった当時においては大変困難をきわめた工事であつだろうと想像される。
それでは、何故この時期に舟を通すことを考え実現できたのか、理由として考えられるのは、全国統一を果たした徳川家康が慶長8年(1603)江戸幕府を開いたことにより、政治の安定がもたらされたことである。次に税として年貢米を江戸、駿府に運ぶ必要が生じたことである。また、内陸の甲斐の国に生活に欠かせない塩を運ぶのに、陸路よりは時間が短縮でき、大量に安く運べる利点があったことである。そして、時代の変遷と共に交易は拡大し、人々の交通手段として欠かせないものとなり、より発展していくのである。
*角倉了以(1554-1614):海外貿易で成功し、後に国内諸河川の舟運を手がける。