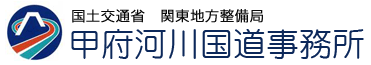かわづくり
-
伝統的治水施設の保全と整備
伝統河川工法
三代目、重年が完成させた雁堤
 雁堤を構成する春の柳堤
雁堤を構成する春の柳堤重年は、祖父や父の治水技術を継承するとともに、甲斐武田氏の技術を参考にし、黄榮宗瑞林寺住職のアドバイスをも受けながら、どんな大洪水をも防御出来る治水策を工夫し研究しました。そして寛文7年(1667)に前代未聞の大工事に着手しました。
それまで水神の岩を挟んで、東と西に別れ、さらに網状の派川となっていた富士川の流れを、岩本から水神の岩まで連なる堤防で東の流れを締切り、富士川の河道を西の流れを一本にするというものです。堤防だけでは富士川の激流を制御することは出来ませんので「亀甲出し」の構造による、岩本1番、2番等の出し水制を造って水を刎ね「土堤出し」構造の備前堤で水流を減勢し、水神の岩を袋の口にして岩本まで続く遊水スペースとしました。これらの相乗によって雁堤の本堤を守り富士平野、加島荘を洪水の氾濫から防御するという構想です。この工事は延宝2年(1674)に完成しました。その時から現在まで330年の歳月が経っていますが今でも私たちは雁堤に護られています。