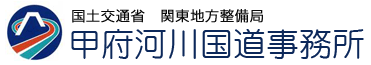かわづくり
-
伝統的治水施設の保全と整備
伝統河川工法
古郡氏の加島荘進出
鎌倉時代の弘安2年(1279)に十六夜日記の著者である阿仏尼が富士川を渡りました。彼女の日記には「明けはなれて後、富士川渡る朝川いと寒し、数ふれば十五瀬をぞ渡りぬる」とあります。
当時の富士川は幾筋もの派川となって流れていたと思われます。古くは加島荘と呼ばれていたこの辺りへ近在の豪族が戦国から江戸時代に進出し水田を開墾しました。その中の一人に須津荘中里の豪族・古郡氏もいました。
古郡氏の先祖は戦国時代の弘治年間(1555頃)に富士市松岡の付近を開墾して籠下村を開きました。戦国時代にはこの辺りは駿河の今川氏、甲斐の武田氏、相模の北条氏の鬩ぎあいの地でしたから支配者がめまぐるしく変わりました。古郡氏が開墾に着手してから半世紀を経た慶長8年(1603)に江戸幕府が成立しますが、その頃には加島荘もかなり開発が進みました。しかし、洪水の被害は頻繁に被っていたようです。 雁が空に翔ぶ姿の雁堤。富士川河口と駿河湾
雁が空に翔ぶ姿の雁堤。富士川河口と駿河湾