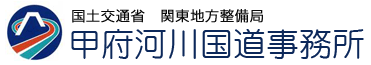かわづくり
-
伝統的治水施設の保全と整備
伝統河川工法
御勅使川の由来と治水の歴史
 巨摩山地を源流に、釜無川にそそぐ御勅使川
巨摩山地を源流に、釜無川にそそぐ御勅使川 甲府盆地の治水の神、三社神社
甲府盆地の治水の神、三社神社甲府盆地の平地部で田畑を耕し、家を構えて安心して生活するにはどうしても釜無川と御勅使川が氾濫しないように堤防や水制などの治水施設を整備する必要があります。ですから、甲府盆地や御勅使川扇状地では、かなり古い時代から治水の努力がされて来ました。「天長2年(825)に甲斐国では大洪水があり釜無川や御勅使川が氾濫して大きな被害が発生したので、当時の甲斐国の国司であった文屋秋津が朝廷に報告し、朝廷はそれを受けて勅使を下向させ、その時に竜王の赤坂に水防の神を三社神社として祀った」と浅間神社の社伝にあります。御勅使川(みだいがわ)の川の名も、この時の勅使の下向に由来するとも言われています。天長2年の当時に水害を被ったと言うことは、既に被害を受ける田畑が開墾され家が建っていた事の証拠でもあります。
現在までも継続されている水防の祭り「御幸さん」がその時から始められたとも社伝にあります。
この盆地の平地部に住み始めた人々は洪水の氾濫から身の安全や財産を護るために治水に対して、いろいろ工夫して来たことが神社等の杜伝や地元の伝承などからも窺えます。 信玄堤は今も、甲府盆地とそこに住む人々を守ってくれている。右が御勅使川
信玄堤は今も、甲府盆地とそこに住む人々を守ってくれている。右が御勅使川