霞ヶ浦の紹介
-
霞ヶ浦の変遷
昔はどうなっていたか/約1千年前
 平安時代(約1000年前)土師器杯念代遺跡(土浦市右籾町出土)
平安時代(約1000年前)土師器杯念代遺跡(土浦市右籾町出土)今から1000年以上前の8世紀当時、霞ヶ浦一帯は、今の利根川下流に広がっていた香取海の入り江のひとつとして香澄流海と呼ばれていました。その面積は、今の2~3倍あり、海水が容易にさかのぼる大きな湖でした。その後、鬼怒川や小貝川が運んできた土砂などが現在の西浦や北浦の湾口に堆積し、現代の姿に近づいてきました。
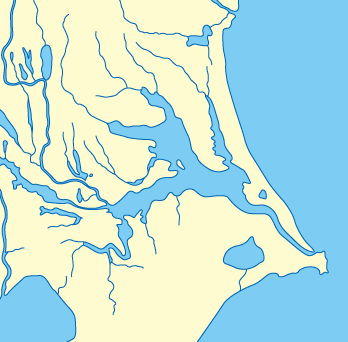
古墳
 船塚山古墳
船塚山古墳 横穴古墳群(崎浜)
横穴古墳群(崎浜)霞ヶ浦北岸の谷津田では、すでに6世紀初頭に開田がおこなわれていたようです。農耕が盛んになるにつれ、沿岸には大小の豪族が誕生し、霞ヶ浦周辺に数多くの古墳を残しました。その中には石岡市にある直径186メートルの壮大な前方後円墳・船塚山古墳や、霞ヶ浦町にある「太子のカロウド」と呼ばれる大陸的な装飾古墳などがあります。
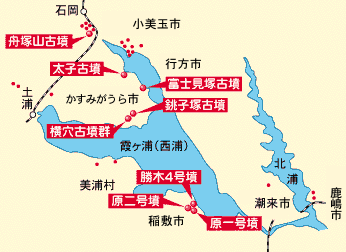 霞ヶ浦周辺の古墳分布図
霞ヶ浦周辺の古墳分布図貝塚
 陸平貝塚
陸平貝塚 縄文土器
縄文土器霞ヶ浦は古くから人々に豊かな恩恵を与えてきました。霞ヶ浦周辺のローム層の中から出土した旧石器は、このあたりに1万年以上前(成り立ち)から人間が生活していたことを示しています。また霞ヶ浦周辺の台地から低地へ傾斜するあたりには貝塚が多く発見されていますが、そこから出土する貝の種類は豊富で、縄文人の豊かな食生活を想像させます。土浦市では鯨の骨も発見されています。
 縄文時代の貝塚と海岸線
縄文時代の貝塚と海岸線

