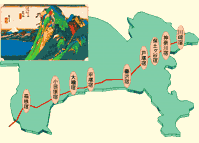![]()
![]()
化粧坂を過ぎると大磯宿へ入る。 かつて宿内神明町と北本町の町境(現国道一号より大磯駅に至る道ぎわ)には土手が築かれ、家並がこの土手により分断されていた。 この土手は火除けのためで、天保七年(1836)九月、五百軒あまりを焼失した大磯宿大火後、安政三年(1856)以降に築かれたという。 宿内北本町山側に、北組問屋場跡。また、北本町のほぼ中央海側にある延台寺には、曽我十郎身代わり石と称する「虎御石」がある。 北本町と南本町の町境、街道山側の地福寺門前入り口の両側に本陣があり、北本町は小島本陣、南本町は尾上本陣と称した。また南本町海側に石井本陣、南組問屋場があった。 ここを過ぎると、東海道は大きく山側に折れ曲がる。山側には高札場跡があり、街道を隔てた反対側に鴫立庵がある。 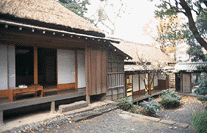 ⑭鴫立庵  |
⑧延台寺の虎御石  虎御前のもとに通う曽我十郎が工藤祐経に矢を射かけられた時、この石が防いだとされ、長さ二尺一寸(約60cm)幅一尺(約30cm)重さ三十六貫(約135kg)ほどの大きさがある。 ⑦地福寺  真言宗京都東寺末の古刹で、かつて家康が利用した「御茶屋」があったところといわれる。また境内には島崎藤村の墓がある。 ⑥小島本陣跡 ⑪尾上本陣跡   |
| 前頁へ |
| 東海道街道図 |
![]()