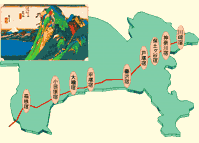![]()
![]()
|
川崎宿と別れ、東海道をさらに進むとやがて旧市場(いちば)村へ入る。右手に熊野神社があり、境内に江戸時代の俳人が鶴見橋を詠んだ句碑が残る。
|
⑨熊野神社と句碑
|

江戸時代以来、地域の核となってきた旧川崎宿は、東京・横浜の発展の谷間となり、やや停滞気味であった。
しかし(一)土地が安価でまとまった工場用地の確保が可能である(二)二ヶ領用水を利用し工業用水が得られる(三)工業原料や製品の輸送が船舶・鉄道とも便利で、隣に首都を控えているなどの利点が注目され、明治三十九年(1906)の明治製糖を皮切りに、東京電気(東芝)、日本コロムビア、富士瓦斯紡績、味の素などが旧宿に隣接する多摩川右岸に沿って次々と工場を建設した。
大正元年(1912)七月、川崎町議会は工場招致を町是とし、これをうけてアサノセメント、日本鋼管、日本鋳造など重工業が進出して、次第に京浜工業地帯の中核が形成された。
大正十三年(1924)七月一日、旧川崎宿を中心とする川崎町と、御幸村、大師町が合併し川崎市が誕生、第二次大戦が激化すると、臨海部をさけ、南武線沿線にも工場が進出した(中原の富士通信・久本の日本光学工業・向河原の日本電気など)。
戦争で市域南部は焼土となったが、戦後の復興はめざましく、昭和四十六年(1971)八月、政令指定都市となり昭和五十六年(1981)、現在の七区制となった。
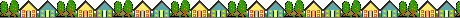
|
|