(3)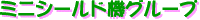 |
 |
製作費4億円のシールド機をミニサイズで作ってしまいました。
しかも、本物のようにカッターヘッド部分を回せるようにして(青い部分)、削った土が内部でどのような仕組みで処理されるかまで図で解説する徹底ぶり、説明の仕方などはもうプロの域でしたぞ。私たちも見習うところ大です。
|
| (写真は、トンネルを掘るシールド機のミニサイズ紹介と、図でシールド機内部の仕組みを解説、シールド機内外のしくみを実に良く説明してました)
|
(4)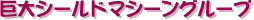 |
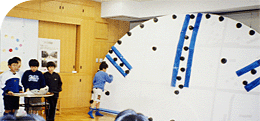 |
な、な、なんと、実物大のシールドマシーンをつくってしまいましたぞ。ただし、議論を重ねた末、校舎天井を壊さぬよう半円を作ることで大きさを実感できるようにしてみました。
これまで学んだ算数を駆使し、棒にひもをつけてコンパスにして円を描き、発泡板を切りました。
|
カッターピットはミニカップラーメンの表面を黒く着色して面板に張り付け、臨場感を出しました。
(写真は、実物大のシールド機のカッターヘッドを説明しています。注目は、半円カッターヘッドの上部が、天井に接触してるところ) |
|
|
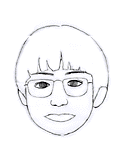

【ミニシールド機グループ】
|
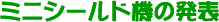
発表会前日、シナリオが思いつかなくてリハーサルがほとんどできませんでした。
自分たちのリハーサルは、すごくゆっくりにしても3分ぐらいで、いくらなんでも早すぎました。他にも自分がセリフをわすれたりしました。
いよいよ発表会です。最初に、ナイス共同溝グループが、げきみたいに司会をやっていました。そして、断面図のも型を作ったズバリ共同溝グループが発表していました。
ぼくは、「発ぽうスチロールで道路をちゃんと表しているし、水道管とかも、色がついていたからすごいなあ」と思いました。
|
そして、いよいよぼく達の発表です。まちがえずに、言えるかどうか心配でした。
「これなら、シールド機の中に土がたまることがなく心配がないですね。」
ちゃんと言えました。ちょっとつっかかったけど、良くできたと思います。
他のグループも、共同溝について、よくわかりました。「未来への一本道グループ」は、感電について、むずかしいのに良くわかる説明をしていました。
共同溝ができるのが楽しみです。なぜなら、電柱が消え、ゆたかな町になるからです。
|
|
|