二瀬ダムについて
-
ダム流域の概況と沿革
二瀬ダム流域の概況と沿革
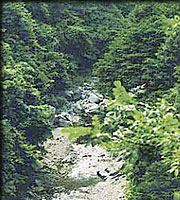 荒川上流域
荒川上流域荒川は、その水源を秩父山地の山梨県(甲斐)、埼玉県(武蔵)、長野県(信濃)境にある甲武信ヶ岳(標高2,475m)に発し、奥秩父特有の深いV字渓谷を流下して秩父盆地を北流し、長瀞を経て寄居附近から関東平野をほぼ南に流れて東京湾に注ぐ、流路延長173km、流域面積2,940km2の我が国の代表的な急流河川のひとつで、その名のとおり荒れる川として昔から数多くの水害の歴史をとどめています。
 荒川河口付近
荒川河口付近特に明治43年の水害は激しく、「埼玉県史」によれば、この洪水で荒川の堤防は右岸で16ヶ所、左岸で19ヶ所も決壊し大きな被害を出したと伝えられています。このためこれを契機に、翌年から直轄で荒川改修工事が始められ、引き続いて大正12年には荒川放水路が掘られ、また熊谷から下流の河道整備等の改修が順次行われ、昭和29年をもってこれら一連の工事は一応完了を見ました。
しかし、この改修工事の途中の昭和22年に計画高水流量(※)を上回る出水をふまえ、昭和25年に「荒川総合開発計画」が立てられ、埼玉県及び東京都の水害に備えることとなりました。この荒川総合計画の中心事業が二瀬ダムの建設です。
※計画高水流量…洪水がダムや遊水池、放水路等の施設により調節されて川に流れる量。洪水から地域を守っていく計画の基本となる。

