事務所の取り組み
-
2. 江戸川の現況
1. 江戸川の形成
江戸時代以前、関東平野東部では河川の流路が乱流し、洪水のたびに川筋が変化する状況であった。
天正18年(1590年)江戸に入府した家康が、当時の利根川を常陸川に導き銚子で鹿島灘に注ぐ利根川の瀬替えを主とした関東一帯の治水事業、世に言う「利根川東遷事業」に着手し、江戸川はその事業の一環として誕生した。当時は利根川の名で呼ばれていたが、東北などからの諸物資を利根川を経て江戸へ運ぶルートの重要性から次第に「江戸川」の名が定着した。
「利根川東遷事業」により、利根川が太平洋に注ぐようになり、江戸川の開削や利根運河の開通で江戸から関東各地への水路が開け、交易が可能となり、江戸川は利根川、江戸川系水運の要として重要な役割を果たしてきた。
舟運の発達は東北、北関東はもとより中山道方面からも大量の物資が江戸にもたらされ、江戸市民の生活を支えることとなり、河岸場の繁栄を通じて沿川の地域開発にも貢献し、関宿、西宝珠花、金杉、野田、流山、松戸、行徳など宿場町としても発展するなど、その後の沿川都市の商工業発展の礎となっていった。(図6)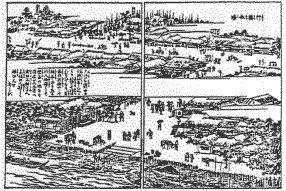 【図6 舟運路と河岸場】 出典:行徳舟場「江戸名所絵図」
【図6 舟運路と河岸場】 出典:行徳舟場「江戸名所絵図」明治以降、近代治水技術を導入した築堤や河道の整備、放水路の開削工事などが行われ、ほぼ現在の江戸川の形が定まった。
江戸川単独での大きな洪水記録はないが、利根川水系として過去の記録をみると、江戸期以降に洪水が頻発していることがうかがえる。記録上最も大きいのは、昭和22年9月のカスリーン台風のときの洪水である。2. 治水機能
沿川地域の都市化による人口増加につれて、江戸川の治水の重要性が高まり、河川改修工事が進められてきた。明治44年から昭和5年にかけては、全川の低水路の拡幅・浚渫が行われるとともに関宿流頭部の改築と江戸川放水路の開削、昭和12年から15年にかけての江戸川応急増補工事により梅郷村(現野田市)地先の無堤部の築堤が行われた。その後、昭和24年の利根川改修改訂計画をもとに行徳可動堰が建設され、昭和30年代から40年代前半にかけて、関宿から野田の間で大幅な引堤工事が行われ、川幅が約2倍となった。
現在は、昭和55年に改定された利根川水系工事実施基本計画(概ね200年に1回程度起こる大雨による洪水に対応。松戸地点で計画高水流量7000m3/sec(図7))に基づき、無堤箇所の築堤、堤防断面不足箇所の表腹付(完成断面での築堤)、漏水箇所・水衝部の補強、下流部構造物の改築、及び河道の掘削等を行っている。また、江戸川沿川の内水対策として、排水樋管及び機場等の能力向上を図っており、中流部右岸地域の慢性的な浸水問題を解決する首都圏外郭放水路事業や中流部左岸の内水排除等を目的とした北千葉導水事業などが実施されている。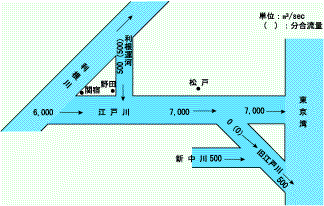 【図7 江戸川計画高水流量図】 資料:江戸川工事事務所
【図7 江戸川計画高水流量図】 資料:江戸川工事事務所さらに、流域の低地地域では調節池の整備や流出抑制対策などの総合治水対策を講じている。
なお、昭和63年には、利根川と分流する茨城県五霞町及び千葉県関宿町から河口部の市川市までの区間(利根運河を含む)において、計画規模を超えて発生すると想定される超過洪水にも破堤しない構造の堤防である高規格堤防を、工事実施基本計画に位置づけ整備を推進しているところである。3. 利水機能
江戸川の水は、上水、農業用水、工業用水として利用されている(図8)。特に上水については首都圏約1,000万人の日常生活を支える水源の役割を果たしており、良好な水質の保全を図ることは重要な課題となっている。このため、江戸川に流入する支川の水を浄水場下流にバイパスする江戸川流水保全水路整備事業が実施されている。
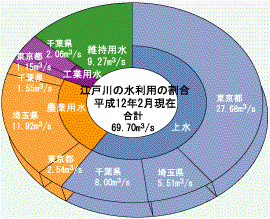 【図8 江戸川からの取水量】 資料:江戸川工事事務所
【図8 江戸川からの取水量】 資料:江戸川工事事務所4. 防災機能
(第4章 3. 河川空間の活用方針、図14参照)
江戸川は、首都圏に大地震が起こり大規模な火災が起きた際の延焼遮断帯として、あるいは、避難地としてなど、防災面に大きな役割を果たす。
また、緊急時に住民を救援し、河川管理施設を復旧するための高水敷を利用した緊急用河川敷道路や臨時ヘリポートとしての活用あるいは舟運による救援が期待される。
東西方向の主要幹線道路と連絡する緊急時の陸上輸送ルートとして緊急河川敷道路が左右岸の高水敷に整備・計画されるとともに、緊急河川敷道路の整備区間内には緊急時の水上輸送ルートを確保するために船着き場が5箇所整備・計画されている。
この他に、河川防災ステーションが5箇所、水防拠点10箇所、水防ヘリポート11箇所、河川敷ヘリポート8箇所が計画されている。
特に、中・下流部における広域幹線道路(常磐自動車道、東京外かく環状道路、京葉道路、東関東自動車道)と江戸川の交差部付近には、成田空港や東京湾という空と海からの支援機能と連携する首都圏東部の広域的な防災拠点形成が期待されている。
さらに、堤防沿いに河川管理用光ファイバーケーブルを布設することによる情報ネットワークの整備が進められている。
また、江戸川の水は、震災時の大規模市街地災害に対応する大容量の消防水利として、重要な役割を担っている。5. 水と緑のネットワーク機能
江戸川は、利根川から東京湾岸地域といういわば関東平野内陸部から海浜部までの自然地、田園地帯、人口集積地を南北に貫く河川として、首都圏東部地域における水と緑の骨格形成軸としての役割が重要視されている。
そのため、高水敷の自然緑地の保全に加え、自然環境に配慮した護岸の施工やワンドの創出など自然機能の保全、回復に努めている。
さらに今後は、江戸川に流れ込む中小の河川や沿川の公園・緑地等を相互にネットワーク化するとともに川の分合流部や都県境などにおいて、大規模緑地拠点形成が期待される。
また、沿川地域では堤外地を中心に稀少動植物や湿地が存在していることから、水と緑のネットワークの形成にあたっては、これら自然環境との調和を図りつつ、進めていく必要がある。6. 歴史・文化、レクリエーション機能
江戸川沿川には、醤油工場(野田市)や矢切の渡し(葛飾区・松戸市)、柴又帝釈天(葛飾区)をはじめとした史跡・寺社仏閣等の歴史・文化施設が多く分布している。また、桜堤や渡しなど観光レクリエーションの場として人々に親しまれている。
江戸川の高水敷は、中・下流部では運動場、ゴルフ場等のレクリエーション施設としての利用が多く、上流部では、牧草地等の自然的な利用形態のほか自然緑地となっている。
また、各種イベントも開催されており、各種スポーツ、花火大会、凧上げ(庄和町大凧公園)、花見等多岐にわたっている。また関宿町等では河川敷の一部がグライダー滑空場として利用されている。

