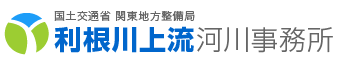利根川の紹介
-
日本一のビッグな川です(概要)
利根川のあらまし
万葉集に詠まれた大河
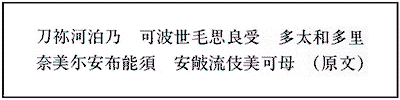 利根川の川瀬も知らす ただ渡り 波にあふのす逢へる君かも
利根川の川瀬も知らす ただ渡り 波にあふのす逢へる君かも利根川の名称が初めて文献に見えるのは「万葉集」です。
「利根川の川瀬も知らす ただ渡り 波にあふのす逢へる君かも」と詠まれています。
万葉集に見える「刀祢河泊」の「トネ」については、これまでいくつかの説がなされてきました。例えば、利根川の水源地が利根郡にあるため、利根郡中には尖った峰が多くその簡略転化によるとするもの、水源の大水上山の別称刀嶺岳・刀根岳・刀祢岳・大刀嶺岳に由来するとするもの、等々です。どうして「とねがわ」というの?
「とねがわ」の「とね」の部分について、そういう名前になった理由はいくつかの説があります。
1.アイヌ語で沼や湖のように広くて大きい川という意味の言葉「トンナイ」を意味する。
2.川の始まる地域(水源地)には高くてとがった峰(みね)「利(と)き峰(みね)」が多いので、その言葉が略されたもの。
3.等禰直(トネノアタイ)、椎根津彦(シイネ<=トネ>ツヒコ)と言う人の名前から呼ばれるようになった。
4.水源の大水上山(おおみなかみやま)の別の呼び方「刀嶺岳(とねだけ)」「刀根岳(とねだけ)」「大刀嶺岳(おおとねだけ)」から呼ばれるようになった。また、利根川の名前が出てくる最初の文献「万葉集」には「刀禰(トネ)」と書かれています。坂東太郎と呼ばれたゆえん
古くは相模国の足柄山・箱根山以東を坂東と呼んでいました。利根川は坂東随一の河川であり、日本の河川の長男として「坂東太郎」と呼ばれ、親しまれていました。これに対して、九州の筑後川が「筑紫次郎」、四国の吉野川が「四国三郎」と呼ばれるようになりました。
データで見る利根川
<322キロメートル 幹川流路延長>
利根川は、信濃川に次いで日本で2番目に長い川。これは、 上越新幹線に置き換えると、東京~新潟間とほぼ同じ距離になります。
<16,840平方キロメートル 流域面積>
流域面積では日本一を誇る利根川。その面積は、埼玉県の約4倍、四国の約80%に匹敵します。
<1,831メートル 水源地・大水上山の標高>
日本列島の背骨の一部である三国山地。利根川の源流は、この三国山地にある大水上山の南面の雪渓です。
<約1,309万人 流域内人口>
総人口の約1/10に相当する約1,309万人もの人々が生活しています。
(調査基準年:平成22年)
<153市区町村 流域内市区町村>
(平成24年10月現在)日本一の流域面積
利根川は新潟県と群馬県の県境にある大水上山(標高1,831メートル)に水源を発し、大小の支川を合わせながら、関東平野を北西から南東へ貫き、千葉県銚子市で太平洋へと注いでいます。
流域内には約1,309万人もの人口を擁し、利根川はその基盤となる生命の水を与え続けています。流域面積は1万6,840平方キロメートルで日本一で、面積でみると埼玉県の約4倍にもなります。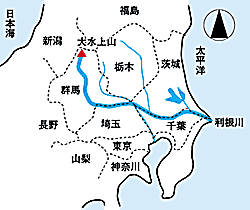 位置図
位置図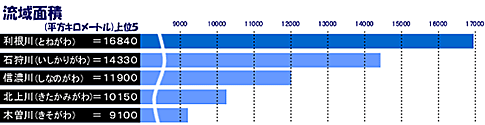 流域面積
流域面積川の長さは日本で2番目
利根川の長さ(河川延長)は322キロメートルで、信濃川の367キロメートルについで日本で2番目です。上越新幹線の東京から新潟までとほぼ同じ長さ。
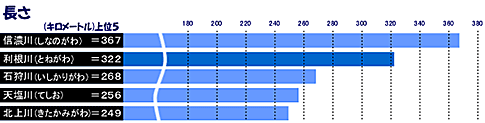 長さ
長さ 日本の主な川
日本の主な川水源の発見は1926年
 利根川水源の碑
利根川水源の碑 利根川源流域
利根川源流域利根川の水源は、長い間、謎でした。明治27年(1894)に初めて組織的な水源探検が行われ、詳しい地図もない中、決死の覚悟で山奥の調査に入りましたが、水源に達することはできませんでした。その後、大正15年(1926)に第2回水源探検を実施し、水源は刀根岳(大水上山)と確認しましたが、地図の不完全さもあり、源流部を解明できませんでした。
そして、戦後、昭和29年(1954)になって、第3回利根川水源調査団がようやく利根川の水源は、標高1,831メートルの大水上山の三角形の雪渓であることをつきとめました。水源を見つけるのに60年の歳月がかかったわけですが、それというのも、水源を求めて険しい山岳を登っていくと、カモシカも避けて通るといわれるほど急峻で危険な箇所がたくさんあったからです。ミニ知識:河川の等級とは?
河川の重要度に応じて、河川法で一級河川と二級河川に区分されています。それ以外の河川については、準用河川として指定し、運用する制度があります。
1.一級河川…国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川で国土交通大臣が指定。(河川法第四条)
2.二級河川…一級河川以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定。(同第五条)
3.準用河川…一級河川及び二級河川以外の河川の中から市町村長が指定。