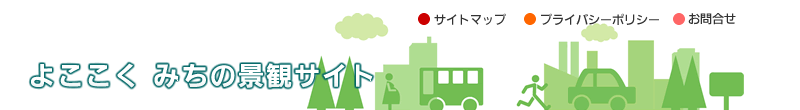
よここく みちの景観サイト
ご存知ですか? 景観法
わが国で初めての景観に関する総合的な法律、景観法。
日本には昔からの美しい景観がたくさんあります。緑豊かな田園風景、歴史的なたたずまいを残す街並み…。しかし、都市化の進展によって、さまざまなビルや看板、電線・電柱等が立ち並ぶようになり、美観への配慮が十分ではない状況が多く見受けられます。そこで、良好な景観づくりのために、わが国ではじめて整備された「景観に関する法制」が景観法です。
景観法は平成16年12月に施行された「景観緑三法」ひとつで、景観法の他に「緑に関する法制」「屋外広告物に関する法制」及び、関連予算・税制の充実から構成されています。
景観緑三法は国・県・市町村が、それぞれ自主的かつ総合的に取り組めるのが大きなポイントです。そして、景観保全に意欲のある住民やNPOが活躍できる仕組みも作られています。また、農林水産省・文部科学省など各省庁が連携して総合的に取り組むほか、地方の固定資産税だけではなく相続税にも踏み込んで、条例で文化的資産を残せるように建築基準法の基準緩和にもおよんでいます。
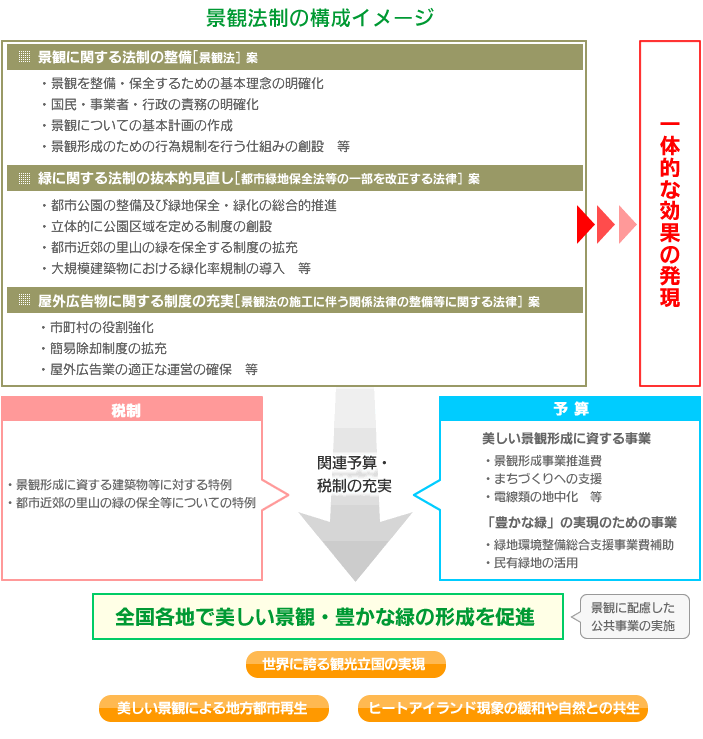
良好な景観は国民の共通資産です。
景観法では、良好な景観は現在及び将来において「国民の共通財産」と位置づけています。そして、都市部だけでなく、農山漁村や自然公園の区域等も含めて幅広く対象として、それぞれの地域が独自の景観形成できるような項目も盛り込まれています。これにより自治体は地域の特徴に合わせた「景観計画」をつくることになります。また、歴史的な建物が並ぶ場所など、積極的に景観形成を図りたい地区があれば、都市計画で「景観地区」に指定することもできます。
良好な景観の形成は居住環境の向上等、住民の生活に密接に関係します。そこで景観計画を支える体制をしっかりと掲げ、住民も積極的に取り組めるよう「景観協議会」の設置や、NPO法人などを景観形成事業者として「景観整備機構」に指定することなども、法的に位置づけています。
景観法の整備により、自治体は景観計画に関して、建物の新築や工作物の設置などは届け出とし、計画上制限に合わないものに対しては変更を勧告・命令できるようになりました。景観地区では、建物のデザインや色なども規制できます。また、関連法令によって自治体が違法として撤去できる広告物の対象を広げるなど、屋外広告物法の一部改正も盛り込まれており、景観を損なうと批判される広告物の氾濫にも対処しやすくなりました。