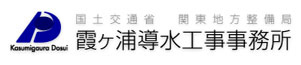霞ヶ浦導水がつなぐ川と湖の環境
-
霞ヶ浦
日本で二番目に広い湖は、その豊かな水で流域を育んでいます
霞ヶ浦の流域は24市町村にまたがり、その面積は2,157km2と茨城県の総面積の約3分の1に相当し、約97万人の人々が霞ヶ浦からの恩恵を享受しています。その流域は全国一を誇るレンコンの生産量などにも象徴されるように、農業、畜産、水産業等が盛んです。霞ヶ浦はそれらの水資源として利用されるとともに、周辺工業地帯への用水としても利用されています。
諸元
流域面積 2,157km2 湖面積 220km2 流域内人口 約95万人 流域関係都県 茨城県・千葉県・栃木県 霞ヶ浦の水利用
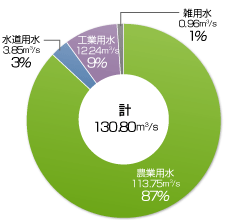 「河川便覧2006」より
「河川便覧2006」より霞ヶ浦の自然
霞ヶ浦は、たくさんの種類の生き物が生息する自然の宝庫です。
シギやチドリ類、サギ類などは一年を通して見ることができます。夏には、コアジサシやオオヨシキリ、冬になると、カモ類などが多くみられます。
湖には、コイやギンブナ、ワカサギなどのほか、ブラックバス、ブルーギルといったどうもうな外来魚も生息しています。地形的な特性により、マコモ、アサザといった水生植物も群生してます。
霞ヶ浦の湖岸やその周辺では、広大なヨシの群落にニホンアカガエルなどの両生類、ニホンカナヘビなどのは虫類ほか、生物たちの貴重なすみかとなっています。魚類
・コイ(コイ科)
流れのゆるやかな砂泥底にすみ、2対のひげが特徴。野生のコイは体高が低い。5~6月、岸辺のマコモなどの水草に産卵します。
・ギンブナ(コイ科)
全体に銀白色をしていて、キンブナより大きくなります。雑食性で、川虫や藻類などを食べます。
・シラウオ(シラウオ科)
半透明でほっそりしています。本来は、春先河口をさかのぼって産卵しますが、霞ヶ浦のシラウオは淡水域で暮らしています。・ワカサギ(キュウリウオ科)
霞ヶ浦の重要な水産資源であり、腹部は銀白色をした全長10cmくらいの細長い魚です。主にプランクトンを食べています。
・オオクチバス(サンフィッシュ科)
灰緑色で褐色の斑紋があります。どうもうでワカサギやタナゴなどを食べ、漁業や生態系に影響を与えています。
・確認されたおもな魚
キンブナ オイカワ トウヨシノボリ ヌマチチブ タナゴなど(西浦で34種、北浦で27種)底生生物
・テナガエビ
流れのゆるやかな泥底を好み、その名のとおり体長の2倍ほどの長さの手を持っています。霞ヶ浦の漁獲量第1位を占めている水産資源です。
・ヤマトシジミ
褐色、または黒色をした二枚貝で食用。淡水、または塩分のある水域の主に砂地にすんでいます。
・確認されたおもな底生生物
ヒメタニシ(タニシ科) イサザアミ(オオユスリ科)などほ乳類
・タヌキ(イヌ科)
雑食性で、沢すじ、湖沼など、水辺の周辺のやぶや山林にすんでいます。足跡はネコに似て丸い形をしています。
・イタチ(イタチ科)
体長は約30cmで胴長、水辺を好み生息しています。おもに夜活動しますが、日中も出歩くことがあります。雪のときは、トンネルを掘ってエサのネズミを探すこともあります。は虫類
・カナヘビ(カナヘビ科)
トカゲに似ていますが、トカゲより尾が長く、体は黒みがかった緑色をしています。
・確認されたは虫類
アオダイショウ(ヘビ科)両生類
・ニホンアカガエル(アカガエル科)
平地の林や草原にすんでいます。赤みを帯びた褐色の体色をしています。1~4月、水田などの流れのない場所に、寒天質に包まれた卵を産卵します。
・確認されたおもな両生類
ニホンアマガエル(アマガエル科)、トウキョウダルマガエル(アカガエル科)、ウシガエル(アカガエル科)など鳥類
・カワセミ(カワセミ科)
水辺の近くのがけによこ穴を掘ってすをつくります。水際の枝の止まって水中の小魚を狙ったり、急降下してその鋭いクチバシに小魚をくわえて舞い上がったりします。
・ゴイサギ(サギ科)
マツ林や雑木林に集団で生活し、夜行性で、昼間は木の上に休み、夕暮れどきになると、群れをなして水辺に飛んできてエサの魚をあさります。クワッ、クワッと鳴きます。
・確認されたおもな鳥
カイツブリ、オオヨシキリ、セッカ、カルガモ、ヒバリなど、32科104種類植物
・アサザ(ミツガシワ科)
だ円形をした葉を水面に浮かべています。夏から秋にかけて葉の付け根に黄色い花を咲かせます。
・マコモ
水中に群生する多年草で、根茎は太く、横にはいます。葉は長さ40cm~1mにも達し、8~10月頃にかけて大きくまばらな花を付けます。
・確認されたおもな植物
カサスゲ(カヤツリグサ科)、ヨシ(イネ科)、ミズアオイ(ミズアオイ科)、ヒメガマ(ガマ科)など78科364種