|
『慶長見聞集』によれば、慶長9年(1604)、江戸幕府は全国的に道路改修事業を起こしたと記されている。道幅を広げ、屈曲をやわらげ、牛馬の往来の妨げとなる小石を取りのぞき、大道の両側には並木を植えるなど、そこには新しい道づくりの方向性が示されている。 |
||||||||||||||||
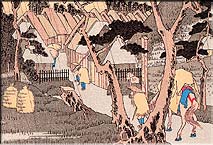 東海道五拾三次之内 大磯「虎ケ雨」 初代広重 保永堂版 神奈川県立歴史博物館蔵 |
||||||||||||||||
|
『慶長見聞集』にこのときの道路改修事業の様子が次のように書かれている。 年久しく治平ならず、諸国乱れ、辺土遠境の道せばくなる所を見はからひ、牛馬のひづめの労を去るやう小石をのぞき、大道の両側に松杉を植え、小河をば悉く橋をかけ大河をば舟橋を渡し、日本国中、民間往復のたよりにそなへ給ふ事慶長九年なり。萬人の思ひをふくみ萬歳を願へあり(『慶長見聞集』1613) 上に「大道の両側に松杉を植え」とあるのは、それまでの柳・桜・梅などの落葉樹よりも、松・杉などの針葉樹のほうが、通行人が夏には木陰に憩い、冬には風をよけられる効果があったからだといわれている。 |
||||||||||||||||
|
上の慶長9年(1604)の道路改修を経て、元和2年(1616)、徳川家康が没すると、江戸時代の道路政策や道路の種類・等級が、家康の遺訓といわれる『家康百箇条』(御遺状百箇条、家康公御遺言百箇条ともいう)に示された。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
次に道路管理について見てみると、家康存命中の2代将軍秀忠の時代の慶長17年(1612)、老中3名の署名により「道路堤等之儀下知」が布告された。そこには道路管理の方法が具体的に示されている。 すなわち「馬が通って生じた窪みには砂や石を敷いて良く固めること、道の傍らは適量の湿りを与えて固めること、道路堤の芝などをはいではならない」などである。 つづいて寛永12年(1635)の3代将軍家光の時代に『武家法度二十箇条』が定められ、道路に関して「道路、駅馬、舟梁等無断絶不可令致往還之停滞事」と道路交通上の停滞を禁じたが、享保2年(1717)にこの主旨が繰り返されていることから、各大名においては必ずしも守られなかったようである。 |