|
江戸時代の村々には、名主(あるいは庄屋)・組頭(あるいは年寄)・百姓代と呼ばれる村役人が置かれ、領主・代官との折衝や村政の運営を行っていた。同じように宿場にも、宿場を円滑に運営するために、宿役人が存在していた。この宿役人が業務を行うために詰めていたのが問屋場(といやば)である。 |
||||||||||||||||||||||
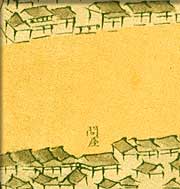
東海道と金沢道の分岐点 (保土ヶ谷)にある道標。 道標には 「かなさわ・かまくら と刻まれている。 |
||||||||||||||||||||||
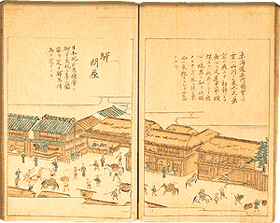
『金川砂子』 駅問屋 |
||||||||||||||||||||||
|
問屋場は、江戸と全国各地の間で送付される幕府の書状の継立(つぎたて)や、参勤交代の大名行列時などに周辺の村々から動員された人足・馬の差配を取り仕切る場所であり、街道に面した宿場の中心に設置されている場合が多かったようである。 |
||||||||||||||||||||||
|
『東海道宿村大概帳』から神奈川県内の東海道各宿における問屋場の所在地をまとめると、次表のようになる。
|
||||||||||||||||||||||
|
一つの宿場で複数の問屋場が存在していることはそれほど珍しいことではなく、戸塚宿では毎月1日〜4日までは矢部町の問屋場が、5日〜11日を吉田町の問屋場が、12日〜晦日までを中宿の問屋場が担当することになっており、また藤沢・平塚・大磯・小田原・箱根の各宿では10日交替で2つの問屋場が担当することになっていた。川崎・神奈川・保土ヶ谷の各宿についても、本来は複数の問屋場が存在していたとも考えられる。 |
||||||||||||||||||||||
|
問屋場には、基本的に次のような役職があった。
|
||||||||||||||||||||||
|
この他にも、「人馬指(じんばさし)」(人足や馬を指図する役職)や「迎役」(参勤交代の大名行列などを宿場の出入り口で出迎える役職と思われる)などがあった。 |
||||||||||||||||||||||

東海道五拾三次之内 庄野「人馬宿継之図」 初代広重 行書版 神奈川県立 歴史博物館蔵 |
||||||||||||||||||||||
|
武士の供が問屋場の役人に書類を提出し、宿役人が証文と思われる文書を確認している。外では人足たちが前の宿場から運ばれてきた荷物を新しい馬に積み替えている。 |