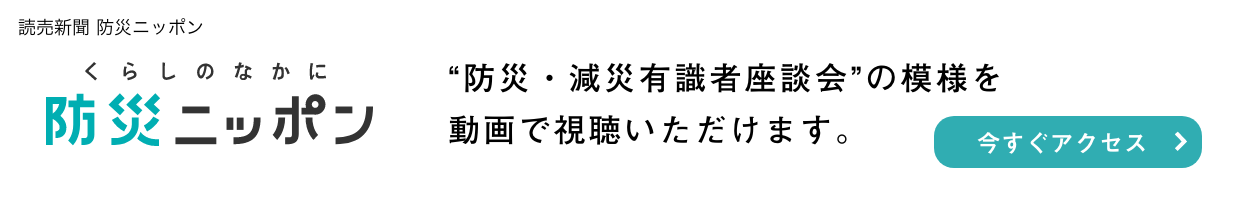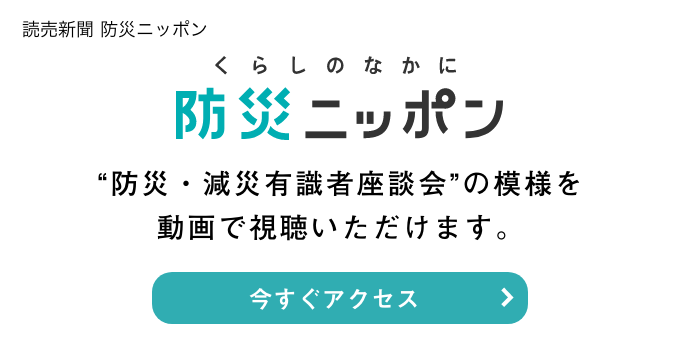防災・減災、国土強靭化に果たす道路の役割
~必ず来る大災害への備えと首都圏の道路~




司会
本日は「防災・減災、国土強靱化に果たす道路の役割
~必ず来る大災害への備えと首都圏の道路~」をテーマに開催します。司会を務めさせていただきます、国土交通省関東地方整備局の野坂周子と申します。
さて、歴史学者の磯田道史先生、国土技術研究センターの徳山日出男理事長、そして国土交通省関東地方整備局長のお三方によります「防災・減災、国土強靱化を議論する座談会」も今回で4回目となりました。今回は3つの小テーマに沿って、最近の災害を振り返りながら、首都圏を支える道路の在り方について議論を深めていきたいと思います。まずは自己紹介からお願いします。
磯田氏 歴史学者をしています。これまでに災害関係の新書を書いたり、歴史漫画を作ったりもしています。
徳山氏 国土技術研究センターの理事長を務めており、電通総研の名誉フェローも兼任しています。東日本大震災のときに仙台で指揮を執った経験が、防災への関わりの始まりでした。よろしくお願いします。
司会 座談会の開会にあたり、関東地方整備局の岩﨑福久局長よりごあいさつをいたします。
岩﨑氏
今年は阪神・淡路大震災から30年、能登半島地震から1年という節目の年でもあります。また昨年は、日向灘沖地震をきっかけに、初めて南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発令されました。さらに全国的に毎年のように発生する激甚な水害などを通じ、改めて日本が常に災害と隣り合わせであることを痛感しています。
首都圏では、首都直下地震が切迫すると言われている上、気候変動による激甚化・頻発化する水害や、道路施設の老朽化も深刻な問題です。こうした状況を踏まえ、防災・減災、国土強靱化における道路の役割、そしていつどこで起こるか分からない災害への備え、さらには生き残るために欠かせない「自分ごと」としての意識づくりについて、ぜひ議論したいと思います。
阪神・淡路大震災から30年、
過去の災害から学ぶもの

司会
最初のテーマは「阪神・淡路大震災30年、過去の災害からの教訓」です。私自身、土木工学を学び始めた年に阪神・淡路大震災が起こり、生涯の仕事としてこの業界を志すきっかけとなりました。
最初に徳山理事長に阪神・淡路大震災30年を振り返って思うことをお聞かせいただければと思います。
徳山氏
この座談会も足かけ4年になりますが、最初のときから一貫して「次の災害はあなたが被害者になるかもしれない。そのとき命を守るために「自分ごと」化しよう。人ごとではない。そして備えるには、教訓を学んで準備をするしかない」ということを主張してきました。
今年は、阪神・淡路大震災から30年、能登半島地震から1年という節目ですが、3月に改めて東北の被災地を回ったとき、語り部の方々が「僕たちの10年は何だったんだろうね?」と言っていたのが印象的でした。能登半島でも「まさか」と思っていたところに地震が来て、多くの方が亡くなった。「これだけ伝えてきたのに、なぜ届かなかったのか」という後悔です。
阪神・淡路大震災にしても、報道は鎮魂がメインになりがちです。それ自体は大切ですが、“どう命を救うか”に結びつく議論が少ない。釜石では石碑を建てるために募集した中に、「100回逃げて100回来なくても、101回目も必ず逃げて」という、友達を亡くした中学生の言葉を取り上げました。空振りばかりでも、最後の1回が本物なら命を守れる、という気持ちです。
でも多くの方が、被災地に対して「頑張ってください」と言ってしまう。被災者からすると、「同情されているだけで、自分たちに災害は来ないと思っている」とも受け止められます。
このように「まさかは来る」という意識を持って、「自分ごと」化することが大事だと私は強く感じています。
司会 磯田先生、今のお話を受けていかがでしょうか。
磯田氏
「頑張って」と言われると、言った側は安心感を得るかもしれませんが、被災者からすると「自分たちとは違う立場」と切り分けられる思いになる。人間の深層心理として「災害は自分に来ない」と思いたい気持ちがあるんだろうと感じます。でも、やはり「まさか」は来るわけです。
歴史学者として、阪神・淡路大震災から東日本大震災、能登半島地震までを振り返ると、「情報が届くスピード」は大きく進歩しましたが、それでも「物資や支援を実際に届ける」段階になると、まだ十分ではないと思います。届ける手段や安全確保は技術が途上で、災害現場に物を運ぶことのリスクや困難さは残っている。
徳山理事長の「100回逃げて・・・」というお話、100回空振りでも1回あればそれが安全につながる。子どもの頃、学校で「机の下に隠れる」としか習いませんでしたが、建物自体が弱いときにはまず外へ逃げる必要があることをあまり教えられていない。弱い建物であったなら、物が降ろうがてんでこに外へ出るという判断。それと垂直避難ですね。水の場合は高さのある場所へ垂直に逃げる。そうした「自分を守る原則」を実践しづらい土壌が日本人にはあり、人間の「安心したい」心理がそれを妨げる。ここを徹底する対策が今も必要だと思います。
徳山氏 「まさか」は必ず来るんだということでしょうね。
磯田氏 ええ、本当に来るんですよね。
災害を「自分ごと」化
するために必要なこと
司会 徳山理事長、以前に「ハワイの津波記念館」についてお話しされていましたが、その例を伺えますか。
徳山氏
私自身、震災を経験してはじめて深く考えるようになったのですが、2013年にアメリカ・オクラホマ州で竜巻が起きた際、2つの小学校の対照的な対応を報道を日本で見たんですね。1つは地下シェルターを準備していた。けれど間に合わなかった場合、教員が柱のある場所に子どもを集めて覆いかぶさるという訓練を実践し、誰も亡くならなかった。一方、別の小学校では7人が亡くなっています。前半は鎮魂の報道でしたが、後半は「なぜ被害がゼロだった学校があったのか」という分析をしっかりしていた。
ハワイの津波記念館でも鎮魂はもちろん、次に命を守るためにどうするかを見せ、伝える姿勢がはっきりしている。日本にもぜひ同じような施設を根付かせたいと思っています。
日本人のメンタリティーと
「オブラートに包む」文化
司会
確かに「シェルターが間に合わなくても、何をすれば命を守れるか」を知る重要性を教えてくれる例ですね。
今までのさまざまな災害を通じ、私たちは多くの教訓を得てきました。その「教訓をどう生かすか」について、改めて徳山理事長お願いします。
徳山氏
報道や世間の反応は磯田先生がおっしゃったように「安心したい」「被災者をいたわりたい」という面が先に出ますし、日本人のメンタリティーとして悪いわけではありません。ただ一方で、「今度は自分に来るかもしれない」という警鐘をどう発するかが弱い。実際に東北の語り部の方々も「自分は子どもを亡くしました」という悲しみを吐露するより、「自分と同じ目に遭わないでほしい」という後悔を強調される方が多い。それが伝わっていない現実があります。
被災地にボランティアで行った方も「自分は同情しに行っていただけで、教訓を学ぼうという意識はなかった」と気づく場合がある。そこを変えないと毎回同じことが繰り返されると感じますね。
司会 岩﨑局長は能登半島地震の後、豪雨の対応でも陣頭指揮を執られました。今のお話を踏まえ、どんなふうにお考えでしょうか。
岩﨑氏
私は過去、中国地方整備局で西日本豪雨災害の復旧にも携わりました。例えば広島の土砂災害や真備町の浸水被害などで「過去の災害の歴史が地域にしっかり伝わっていなかった」と痛感しました。そこで重要なのが「自分ごと」化です。
能登半島地震については、発災直後の道路啓開に当たって、地元の建設業者の皆さんや日本建設業連合会、自衛隊とも連携し、物資や重機を海から運び込みました。被害が大きかったのは県道や市町道ですが、「権限代行」制度を使って国が進めたり、交通マネジメントで優先車両のみ迂回させたりと、多様な取り組みを行いました。さらに道の駅などを防災拠点として使い、トイレ・入浴機能を備えたコンテナを全国から集めて避難所で活用したりもしました。
ところが9月には豪雨が襲い、復旧作業中にもかかわらず被害が重なった。複合災害のリスクは首都圏でも同様で、首都直下地震の後に水害や高潮が起きるおそれもある。そうした連鎖を念頭に備える必要があるという教訓を得ました。
司会 昨年度の座談会でも能登半島地震は大きな議論のテーマでしたが、その後、9月の豪雨も重なりました。これに関して磯田先生いかがでしょう。
磯田氏 今までの災害を見ても、同じようなパターンが重なることが多い。ですから科学的知見と歴史からの知恵を組み合わせて、後世に継承する仕組みが大事です。人生100年という時代、1万年に1回クラスの現象でさえゼロではない。徳山理事長が取り組まれている防災資産のように、各地域で得た知恵を次世代にきちんと伝え続けるのが重要だと思います。
地域の取り組みと防災資産の意義
司会 防災資産のお話が出ましたがご説明いただけますか。
徳山氏
これは国土交通大臣と内閣府防災担当大臣が認定する制度で、昨年、最初の認定として11カ所を選びました。趣旨は「次の命を救うために活用できる資産を増やそう」というもの。例えば、新潟県関川村の「大したもん蛇まつり」は、長さ82.8mの大蛇を藁で編んで担ぐ行事です。82.8という数字は、50年前に大きな被害を出した“羽越水害”が8月28日に起きたことにちなむ。お祭りに参加することで、村の人々は自然と「羽越水害」の教訓を思い出せるわけです。
東北の「3.11伝承ロード」もそうです。観光だけでなく「教訓がいのちを救う」というメッセージを明確に掲げています。いずれも鎮魂だけで終わらせず、「同じ悲劇を繰り返さないためにどうするか」を伝え続ける活動を評価し、認定しているわけです。今後この取り組みを広げていきたいと思っています。
磯田氏 関川村の「大したもん蛇まつり」は、私が選考委員を務めるサントリー地域文化賞で受賞しています。災害自体は悲劇ですが、一方でこうした形でまちおこしにつなげ、災害の記憶を風化させない工夫をされているのは大きな意義があると思います。
徳山氏 本当に面白いやり方ですよね。
リスクマネジメントと
クライシスマネジメントの違い

司会 災害を知ること、それをどう教訓に生かすかという話が出ていますが、今回は道路をターゲットにしています。災害後の道路啓開のような事後対応と、事前の備えの両面があると思います。次のテーマとして、「リスクマネジメントとクライシスマネジメントの違いと道路が果たす役割」を取り上げたいと思います。「リスクマネジメントとクライシスマネジメントは何が違うのか」という点を岩﨑局長から説明していただければと思います。
岩﨑氏
リスクマネジメントとは、災害を含む危機が起きることを想定して、被害を最小化するための備えを平時・事前に進めておく概念だと考えています。国土強靱化の取り組みもその一環です。例えば「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」を令和3年から進めており、今年が最終年度に当たります。
道路分野では強い幹線道路ネットワークの構築が重要です。能登半島地震でも課題となりましたが、災害に強い道路を整備する必要があります。ミッシングリンクの解消や2車線から4車線化、ダブルネットワーク化などが挙げられますし、老朽化対策も急がなければなりません。
また、市街地では地震が起きると電柱が倒壊し、道路を塞いでしまうおそれもあり、無電柱化を進めることも重要です。こうした事前の備えがリスクマネジメントです。
一方、実際に災害が起こった後、いかに迅速に社会を立て直すかがクライシスマネジメントです。首都直下地震が発生した場合、都心に向かう8方向から啓開ルートを確保し、72時間の壁を意識して48時間以内に少なくとも各路線で1ルートは開通させる計画を立てています。道路だけではなく河川や海、空路も合わせた4路の連続性を確保し、物資や人員を集中投入できるようにするわけです。
この際、国土交通省のTEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)が現地で被害状況を調べたり、応急給水や電源の確保、ドローンによる状況把握などを行います。事前と事後の両面から取り組みを強化し、総合力を高めていきたいと考えています。
司会
クライシスマネジメントの中心になる道路啓開を、法律改正にまでつなげてくださったのが徳山理事長です。一方、リスクマネジメントとしては、先ほど局長も触れられた無電柱化など、事前準備が必要な課題が多くあります。
私自身、大学時代に阪神・淡路大震災の航空写真を分析し、魚崎や長田でどの幅員の道路がどのぐらいがれきで埋まり、消防・警察がどれだけ活動を阻害されたか、倒れた電柱の影響はどれほど大きかったかを研究していました。現在は関東地方整備局で「8方向作戦」にかかわっていますが、電柱が数本倒れただけで72時間以内の通行を諦めざるを得ない道路も出てきます。その意味で、無電柱化をもっとスピード感を持って進める必要があるのではと強く感じていますが、現実にはなかなか難しい面もあります。
リスクマネジメント・クライシスマネジメントの視点で、道路の備えについて磯田先生はいかがでしょうか。
磯田氏
災害前の備え(リスクマネジメント)と災害後の対応(クライシスマネジメント)は、どちらも大事ですね。事前の備えは、壊れにくい道路やネットワークを整えておくこと。実際に災害が起きた後は道路啓開が中心になりますが、従来よりも災害法制が整ってきたことで、危険な建物などを緊急に撤去しやすくなったのは進歩です。
ただ、自然災害はときに大きく地形を変えてしまいます。能登半島地震の事例では地面が隆起した所を活用して代替道路を造った例もありますが、逆に沈む場合は場所自体が使えず対応が困難になることもある。さらに川の氾濫や津波で道路が浸水し、車両や人が逃げ遅れるリスクもあります。
阪神・淡路大震災のときは、がれきであっという間に道路が埋まったことが印象的でした。震災時、東京から帰って来た妹が「道幅って本当に大事」と痛感したそうです。普段「広過ぎる」と思うような道路でも、いざ災害が起きればすぐにいっぱいになってしまう。そういう現実を踏まえて、事前に“余裕”を見込む必要があると感じます。
余裕ある街づくりと“道幅”の重要性
司会 災害時に細街路ががれきで埋まると、火災が起きても消防車両が通れないという実態を私も研究しました。こうした課題へのソリューションを考えるとき、徳山理事長は「ただ悲しむだけでは次の被害を防げない」とおっしゃっていますがいかがでしょうか。
徳山氏
磯田先生が「余裕が大事」と言われたのは、日本人の考え方に通じる問題だと思います。平時のベストな状況ばかり想定してしまうと、いざというときの備えが削られてしまう。橋にしても、昔の新潟の萬代橋や日本橋などは、四隅に公園のようなスペースがあって、洪水で橋が流された際に“仮橋を架ける”ための場所だったわけです。でも今は都市部でビルが並び、予備のスペースがほとんどありません。
こうして“余裕”を削ぎ落としていくと、将来必ず行き詰まる。磯田先生がおっしゃるようにいろんな想像力を持って、平時だけでなく最悪の事態を想定した余地が必要でしょう。
磯田氏 人間の気持ちにも道幅があると思うんです。災害とは関係なさそうな雑談やユーモア、近所でのちょっとした会話など、“余計”なやり取りもふだんから持っていると、「あの人が最近姿を見せないね」と気づけたりすることがある。そこが実は災害時の命を救う手がかりになったりもします。余白や余裕というのは社会のあらゆるところに必要だと思いますね。
徳山氏
リスクマネジメントとクライシスマネジメントを区別しないまま危機管理という言葉だけで済ませると、議論が混乱しがちです。起こる前の備えと、起きた後の対応はまったく時間軸も違う。しかし同時に、別物ではあるけれど密接に関連しているという面があるんですね。
私が震災後、東北で1年間活動してから書いた「災害初動期指揮心得」という本では、1ページ目に「備えていたことしか役に立たなかった。備えていただけでは十分ではなかった」と書いている。大災害の最中に急にリスクマネジメントは整えられないので、やはり事前の準備が重要。ただ毎回災害のパターンは変わるので、準備したものをどう臨機応変に使うかも問われます。
特に道路は、救命・物資輸送・医療など、あらゆる支援の最初の基盤になる。「まず道を通してくれ」という訴えがどの災害でも必ず出てくる。その重みはもっと多くの人に共有してもらいたいですね。
土地権利の壁と“公益”のジレンマ
磯田氏
日本は土地の権利意識がとても強い国です。江戸幕府や明治政府でも、土地収用を強引に進めると強い反発にあってなかなか進まない。歴史を見ても、オランダ人が「こんなに農民の権利を認める国は珍しい」と驚いたほどです。
やはり人口が密集して、土地の価値が高いことが背景にありますが、それが道路拡幅などを阻んでしまう面もある。一方で、私権が守られる文化が根付いているともいえます。本当に難しい問題ですね。
司会 道路を造ろうとすると地元説明会で歓迎されない経験もありました。そもそも道路が持つ公益的な役割を伝える努力を、私たちが十分にしてこなかったのかもしれません。
磯田氏 戦時中の軍国主義下では容赦なく土地収用が進んだ例もありますが、今はなかなかそうはいかない。ただ、昭和20年代に名古屋で造られた100m道路や防空緑地などは、結果として今の災害対策に大きな効果をもたらしています。もちろん当時、収用で苦しんだ方の涙があって成立したものなので、そこへの感謝の気持ちは忘れてはいけません。
徳山氏 本当に歴史を振り返ると、災害を語るだけでここまで大きな視点に広がりますね。
司会
まさに歴史の積み重ねが今の都市形成に生きているわけで、「悲劇や強制」として終わらせるのではなく、私たちがその価値をどう受け止めて次に備えるかが問われていると感じます。
防空緑地や昭和20年代の名古屋の100m道路もそうですが、当時に造られた資産に救われている面がありますよね。
磯田氏 そうなんです。あの時代、地主さんたちの泣きの涙でできた安全性。なので私たちはそこへ本来、感謝すべきだと思います。京都に烏丸通や堀川通、五条通など幅の広い道路がありますが、あれも当時の整備でできた部分があります。地元の方々からは「実はあのとき、強制的に土地を取り上げられまして」と悔しそうに語られることがあるんですね。何もやっていない私たちが聞くと申し訳ない気持ちになりますが、その方々の犠牲によって生まれた遺産が今の安全性に結びついている。まさに悲しい遺産だと痛感します。
「自分ごと」化が導くもの

司会
日本特有の困難はありますが、諦めている場合ではありません。次のテーマは「自分ごと化が導くもの」です。今回が4回目の座談会となりますが、最初に徳山理事長にレクに伺った際、「自分ごと化を訴えているけれど、本当に効果が出ているのか?」という疑問を提示されました。そこから、どう“意味のあるアクション”につなげるかが今回の焦点です。
竜巻の例でいえば、シェルターがなくても身を守る方法はあります。かといってシェルターの整備自体が無駄ではありません。道路においても同じように「自分ごと」として理解し、どう具体的な行動へと生かすか。そのあたりについて、ご意見をお願いします。
徳山氏
これは果てしない挑戦ですが、3月に東北の語り部さんたちと話したときの「俺たちの10年は何だったんだろう」との話。それでも諦めずに繰り返し訴え続けてくれています。災害は「いつ来るのか」「何%の確率なのか」という報道が多いですが、本当は「いつ起きてもおかしくない」ものなので、そこばかり注目しても意味がない。例えば津波のリスク地域なら、「地震が来たら一目散に逃げましょう、空振りでも構わない」と徹底させるべきです。
ところが、災害だけは「手を合わせて忘れないようにしよう」という鎮魂に終わりがちで、「具体的にどう命を守るか」の話へ繋がらない。「次はあなたかもしれない。こう備えてください」と言い続けるしかないんです。どれだけ繰り返しても変わらない面はあるけれど、続けなきゃならない。工夫しながら粘り強く広めるしかないですね。
司会 続けること自体に意味がありますね。
徳山氏 ええ。続けるしかないし、さらに工夫を積み重ねる必要があります。前回触れた「防災資産」もその一例ですね。
「自分ごと」化の実感と
富士山噴火のリスク
司会 磯田先生はいかがでしょうか。
磯田氏 「自分ごと」化は本当に重要です。私は古い町屋が多い京都に住んでいて、先日、妻と行ったレストランが“1階部分を駐車場にしている町屋”でした。前をトラックが通るだけで揺れる建物で、「ここがもし直下型地震に襲われたらどう倒壊するか」を頭の中で想像してしまうんです。もっとも、あまり深刻になり過ぎると生活が成り立ちませんが、「もし倒れたら、どの部分を壊せば救助できるか」という意識を持っておくだけで違う。
司会 最近話題に上がっている「富士山噴火」についてですが、磯田先生の本では「富士山噴火が起こったらゴーグルが飛ぶように売れる」と書かれていました。
磯田氏 火山灰はガラス質なので目に入ると大変痛い。
司会 ちょっと突飛な災害に見えても、実は「ゴーグルを備える」という“身近なアクション”に落とし込めるわけです。火山灰はガラス質で目に大きなダメージを与えるため、ゴーグルの備えが有用です。富士山噴火は雪よりはるかに重い火山灰が積もり、建物の圧壊リスクも高まりますが、歴史的に見ていかがでしょうか。
磯田氏
火山の噴火は、噴石や火山灰が大量に降り注ぐだけでなく、河川を泥流で埋めて洪水を多発させる点が厄介です。江戸時代に浅間山が噴火した際、川底が埋まり、それ以降洪水が頻発し、幕府や藩が財政的に苦しんだ。その経験からすると、たとえば富士山が噴火した後、梅雨や台風シーズンに入れば「泥流+豪雨」の複合災害も想定されます。
こうした状況でも、現代はある程度の対策が可能になってきましたが、問題は“事前の準備”です。大量に降った火山灰をどこに捨てるか。環境面や埋め立て許可の問題が絡むので、一筋縄ではいきません。
「地方巧者」としての役割
~現代の国土交通行政~
司会 岩﨑局長、「火山と河川氾濫」の話を受けていかがでしょうか。
岩﨑氏
今は現代の地方巧者といったところでしょうか。浅間山噴火による洪水被害が起きた当時と違い、吾妻川には八ッ場ダムがあります。令和元年の東日本台風(台風第19号)では試験湛水中だったこともあり、下流の利根川への流量を抑え、ぎりぎりで氾濫を防ぎました。また、東日本大震災を受けて「浅間山の泥流が起きたときに効果があるか」を検討していた経緯があります。こうして江戸時代以来の災害教訓が少しずつ活かされているわけです。
もっとも、財政的な制約の中でバランスを取りつつ、安全に資する設備を整えるのは簡単ではありません。だからこそ、私たち国土交通省は住民にとって頼りにされる存在でなければならないと感じます。
司会 河川やダムに加え、最近は気候変動で洪水や土砂災害が頻発化していますし、「流域治水」という考え方が注目されています。
岩﨑氏
ハード整備だけでは守り切れなくなってきているという現実があります。平成27年の関東・東北豪雨、平成30年の西日本豪雨、令和元年の東日本台風などを経て、住民側も「自分たちの命は自分たちで守る」という意識を強めていかないと被害を防げない。要は、リスクのある場所には住まないとか、被災の可能性を知り備えることで、「自分ごと」として捉えて取り組んでいただくことが重要であり、そういった施策を流域治水というふうに銘打って実施しているところです。
同じように、首都直下地震の際の道路啓開にも関わりますが、無電柱化が進まないのは、通信事業者や関係各所の理解を得るのが難しいからです。そこで、「災害のときにはこうなる」という現実を「自分ごと」として捉えてもらう。その上で協力を進めることが不可欠だと感じています。
司会
昨日は「地震時の道路啓開」をどうするか議論していました。災害現場ではがれきや土砂を道路脇に寄せながら片側通行を確保するのが一般的ですが、富士山噴火の火山灰は側溝に押しやれば詰まってしまう。それなら中央分離帯側に寄せておくべきか。あるいはどんな重機なら効率よく除去できるか。具体的に想定しておかないと、いざというときに動けません。そこを学んでいきたいと思っています。
最後に徳山理事長に、「自分ごと」化の真の意味や今後の進むべき方向を伺います。
徳山氏
富士山噴火は、私も考える限り「いちばんややこしいリスク」です。いつ噴火するか分からないし、降灰はほぼ確実に広範囲に及ぶ。さらに、火山灰の処分方法もそうですが、想定していなければ何も手が打てません。
磯田先生がおっしゃったように、どこかで「突き抜けて考えておく」必要がある。日常的にずっと災害を意識し続けるのは心が疲れますが、たとえば京都の町屋なら、「崩れるとしたらこうなって、どこを壊せば救助できるか」を一度は本気で想像する。マニュアルがあっても停電で校内放送が使えない、ガラスが割れて通路が塞がるかもしれない――そういうちょっと考えれば分かるはずの事態にも、人は直面するまで気づかないのです。
この座談会ではずっと「自分ごと」化をテーマに議論してきました。鎮魂や伝承も大事ですが、「命を守るための備え」の話をもっと取り上げなければいけない。たとえば首都直下地震であれば、まずは家が崩れないように耐震性を高めるとか、家具を固定するほうが飲料水の備蓄より先に必要という場合もある。こうした情報を伝え続ければ、一人でも命を守れる可能性が高まる。それが私たちの目指すところではないでしょうか。
“人ごと”にならない想像力
司会
本日は3つのテーマにわたり議論を進めてまいりました。どうやって具体的なアクションに結び付けるか、どうやって具体的に命を守る世界をつくるか、その中で道路行政としても貢献できることは何か、多くのヒントをいただけたと思います。
座談会を締めくくるにあたり、お一人ずつ一言ずつお願いいたします。
徳山氏
関東大震災の報道を見ると10万人以上が亡くなり、その8割以上が焼死という事実ばかり強調されがちです。しかし、今言われている首都直下地震は、必ずしも同じタイプ(マグニチュード8クラスの相模湾直下)ではなく、マグニチュード7程度の直下型と想定されています。シミュレーションによっては、火災よりも揺れの被害がより深刻だという見方もある。最大2万3,000人の死者が想定されるといわれる一方、条件次第で死者数が大幅に抑えられる予測もある。そうした違いを理解せず、「とにかく火災が恐いから火を消せ」などと一辺倒で報道されると誤解が生じる。
私たちは正しい知識を広め、本当にみんなが助かるように貢献したいと思います。
磯田氏
特に印象に残ったのは被災者に「頑張って」と言うと、うれしくないというお話です。私たちも患者さんに向かって「頑張って」と言うのは気を付けたほうがいいと聞きますが、なるほどと思いました。
「頑張って」と声をかけると、被災した人だけが当事者で、声をかける側は見物席にまわってしまいます。自分とは違う人として切り離してしまうわけです。ではどう言えばいいか、「人ごととは思えません」が適切ではないかと思いました。そうすれば同じ土俵に立てます。
そこからさらに一歩踏み込んで、「もし自分がその立場だったら」を深く具体的に想像することが「自分ごと」化だと感じます。地震の揺れでガラスが降り注ぐかもしれない、津波が道路を塞ぐかもしれない、そういう“現実を想像する”力こそがホモサピエンスの特性。実際には起きていないことを想像するからこそ備えることができるんだと思います。
体験と想像力を共有する場づくり
岩﨑氏
お二方から「自分ごと」化を進めるうえで、具体的な想像力をどう高めるかというお話がありました。私も疑似体験を通じた想像力向上が大事だと思います。たとえば、東京・有明にある「そなエリア東京」では、地震発生後の72時間を想定したシミュレーションを体験し、公園への避難から避難生活まで一連の流れを追体験できます。そこでは命を守るための“100のそなえ”をスマホなどで習得することも可能で、想像のきっかけを提供しています。
関東地方整備局としては、地震、水害、土砂災害、火山災害まで再現できるバーチャル体験車も用意していますので、そうした取り組みを広めながら、「自分ごと」化を進めていきたいと考えています。
司会 本日いただいた教訓を胸に、私たち関東地方整備局としても道路行政をしっかり取り組みつつ、こうした情報を伝えることで、一人でも多くの方の命を守る世界を目指していきたいと思います。本日は大変貴重なお話をありがとうございました。