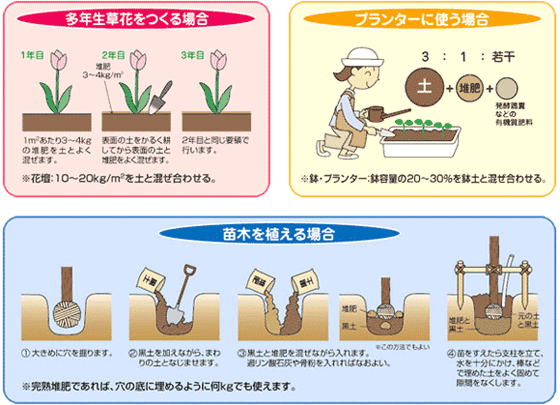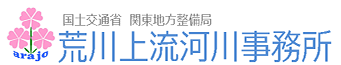事務所の取組み
-
維持・管理
荒川緑肥
荒川上流河川事務所では、河川の安全や環境を守るために春から秋にかけて堤防の除草を行っております。
環境への負荷の軽減や刈草の有効利用を目的とした「緑のリサイクル」の推進として刈草の堆肥化を行っています。令和7年度の応募について
今年度の応募は終了しました。
○東松山ヤード・大里ヤードにつきましては、多くの方にご応募いただいているため、配布量を調整させていただく予定です。
ご応募予定の方は、ぜひ朝霞ヤードでの受け取りをご検討ください。
○応募者多数の場合は、配布量を調整させていただく場合があります。返信はがきにて連絡させていただきます。
○応募はがきに不備がある場合、無効とする場合があります。応募方法の詳細を確認いただき、必要事項に不備の無いよう記載をお願いします。
○土日・祝日の配布は行っていません。
問い合わせ先
国土交通省 荒川上流河川事務所 荒川緑肥事務局
受付時間 平日9:00~12:00 13:00~17:00まで
電話049-246-1031
★応募方法の詳細はコチラ★ [PDF:602KB]
令和7年度成分表示[PDF:27KB]
よくある質問[PDF:109KB]
1)応募方法
次の事項を記入して、必ず「往復はがき」でお申し込みください。
➀氏名、➁郵便番号、➂住所、➃電話番号、➄受取ヤード名
➅希望緑肥量(kg ) (※10kg単位でご応募ください)
➆希望する受取月日及び午前又は午後(第3希望まで記入してください)
➇その他意見など、➈台数( ※トラック受取の場合記載してください)
受取日は、下記の月日から選び、
午前・午後を含めて第3希望まで記入してください。
・午前 9時から11時まで
・午後 13時から15時まで
■袋詰めによる受取日
・令和8年1月19日(月)・1月20日(火)・1月21日(水)
・1月22日(木)・1月23日(金)
・1月26日(月)・1月27日(火)・1月28日(水)
・1月29日(木)・1月30日(金)
■袋詰めせずトラックの荷台に直接積み込む場合の受取日
・2月2日(月)・2月3日(火)・2月4日(水)
2)応募先
〒350-1124 埼玉県川越市新宿町3-12
荒川上流河川事務所 管理課 荒川緑肥事務局 あて
3)応募期間
令和7年10月14日(火 )~12月5日(金)まで(当日消印有効)
4)当選発表方法
〇応募者多数の場合は希望数量より受取量を調整させて頂きます。
〇当選返信はがきを「荒川緑肥配布予約券」とし、発送をもって発表に代えさせていただきます。
〇発送は、1月中旬 を予定しています。
〇なお受取月日、受取量については返信はがきにて連絡させていただきます。
5)応募規則
〇はがきは1家族1枚限りとします。(複数枚数及び複数名での応募は無効とします)
〇販売等を目的としている方には配布できません。
〇必要事項の記載不備、応募期間外の応募は無効とさせていただきます。
〇※悪天候の場合、袋詰めおよびトラック荷台積込を予備日に振替える場合があります。
予備日:令和8年2月5日(木)~2月6日(金)
6)配布方法
〇堆肥は袋詰していないバラ(山積)の状態のものを配布します。
〇袋詰は各自でお願いします。スコップは当方で用意します。
〇袋は各自で土のう袋、厚手のビニール袋などをご用意下さい。
〇トラックの荷台に直接積み込む方法での受け取りも可能です(指定日のみ)。
〇この場合、重機により積込を行います。なお、配布場所及び道幅の一部が狭いため、トラックは、2t以下の車両までとします。
7)最大配布量
〇東松山ヤードは最大350kg、大里ヤード・朝霞ヤードは最大1,000kg まで
応募多数の場合、調整させて頂く場合があります。
8)配布箇所
下記の3つの堆肥ヤードで配布を行います。(詳細位置図を参照してください)
【1】大里堆肥ヤード・・・・熊谷市津田新田2024-24付近
【2】東松山堆肥ヤード・・・東松山市下押垂 526 付近
【3】朝霞堆肥ヤード・・・・朝霞市下内間木106付近
※電話での問い合わせはご遠慮ください。現地までの道案内は致しかねます。
9)注意事項
〇返信はがきに記載された月日時間帯に、直接堆肥ヤードに来てください。
〇当日は、受付→積込み→計量の作業順序となります。
〇受け取り時にご持参いただくもの・返信はがきの「荒川緑肥配布予約券」・袋 ・手袋
〇堆肥の品質は不安定です。(小石やゴミ等が混入している場合があります。)
〇堆肥の使用により損害等が生じても、当所は責任を負いません。
10)その他
ご記入頂いた個人情報は厳重に管理し、「荒川緑肥無償配布」以外の目的で使用することはありません。
誕生までの経緯
国土交通省では河川等の公共施設における緑地の管理によって発生する刈草等を有効活用するための施策として、平成6年7月に策定した“緑の政策大綱”や平成8年度から5ヶ年実施された“緑の推進五箇年計画”等、緑の保全、創出、活用に向けた展開を図ってきました。
河川敷はもちろんのこと、街路樹や公園等から発生する剪定枝や刈草等の植物発生材を、堆肥として再利用する試みが全国各地で行われてきています。
当事務所でも「緑のリサイクル事業」の一環として、平成7~9年にかけて堤防の刈草による堆肥化実験を行い、平成9年12月にこの堆肥を「荒川緑肥」と命名して埼玉県に届出をしました。製造方法
(1)除草
堤防の草を刈ります。(5月頃)
(2)破砕
刈草を3cmを目安に細かく切ります。
(3)仕込み
細かくした草に水を加えて発酵準備を整えます。
時間の経過とともに発酵が始まります。時間の経過とともに温度が変化し、この発酵温度が堆肥の完成を大きく左右します。発酵状態を把握するため、仕込みから完成までの期間を通して、仕込み後30日間は毎日、その後完成まで1週間に1回、温度を測定します。発酵温度の最高値はおよそ75度まで達します。
(4)切返し
発酵を均一にするため、仕込みから2週間後、1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後を目安にかき混ぜます。空気の流れが良くなり、微生物の活動が活発化し、さらに発酵が進みます。
(5)仕上げ
完成した堆肥は粒の大きさを揃え、また、ゴミなどを取り除くため、ふるいにかけます。家庭での利用方法
荒川緑肥は、家庭菜園や園芸用に利用できます。